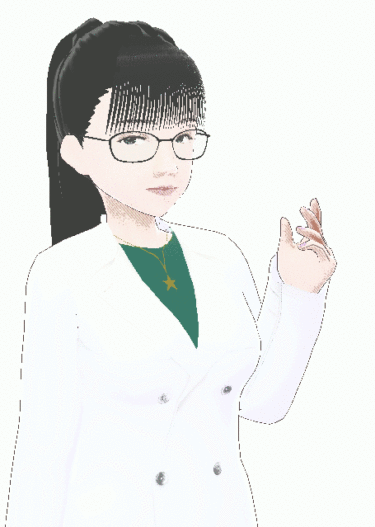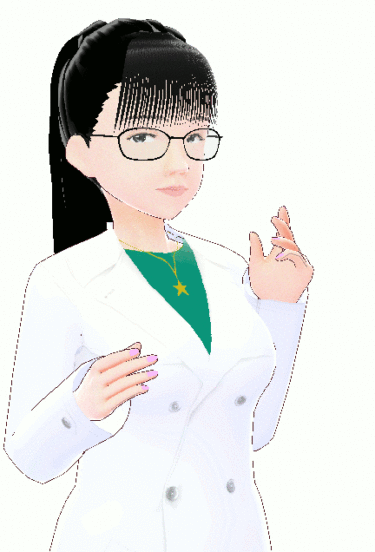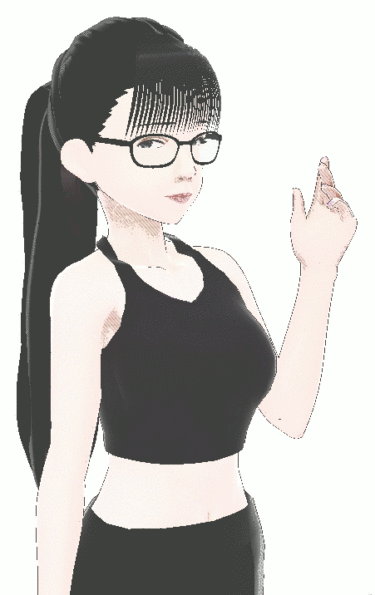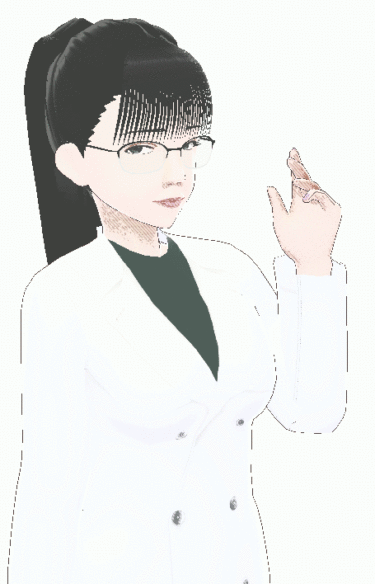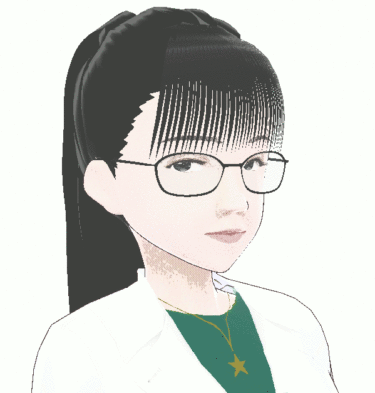健康食品では、特定保健用食品や機能性表示食品で決められた機能を表示する以外は、効能効果を標ぼうすることはできません。
もし、効能効果を標ぼうした広告などを行うと、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に抵触してしまいます。
健康食品の脱法広告
『脱法』というと、脱法ドラッグを連想する人もいるかと思いますが、健康食品などでは、法の目をかいくぐるようなテクニックが横行しています。

例えば、検索エンジンで調べていると、「●●乳酸菌」というバナーがでてきて、そこには「えっ?56日で花粉症、鼻炎、アトピーの症状が軽減? アレルギー症状の改善が期待できる、特別な『●●乳酸菌』とは?」とキャッチコピーが記載されています。
そこでそのバーナーをクリックしてみると、「日本を代表するアレルギーの名医が解説する研究成果、花粉症対策と注目の『●●乳酸菌』のタイトルに、鼻を手で押さえた女性やマスクした男性の画像もでてきます。
そして、名医と称するドクターが花粉症の発症メカニズムとともに『●●乳酸菌』の有効性を解説しています。
これは、特定の商品名は一言も出てきていませんので、これはあくまでも『●●乳酸菌』という成分の学術的な説明ということが言えます。
しかし、しばらくニュース記事を閲覧していて、再び検索エンジンのページに戻ると、今度はとあるサプリメントの広告がでてきて、『●●乳酸菌配合 ***』となって商品画像も出ています。
これは商品名がズバリでているのであきらかに健康食品の広告ですが、ここでは『●●乳酸菌配合』とは書いてあるものの、効能効果に関連するようなことは書かれていないので、これだけをもって医薬品医療機器等法(旧薬事法)に抵触するとはいえません。
東京都の広告監視
以前から東京都では、健康食品の広告監視などで、新聞紙面の上段で成分の効能効果を説明しておいて下段でその成分を配合した商品を広告したり、雑誌の異なるページに広告を掲載したりする場合、「別々の広告とは判断しない」としています。
新聞上下で分ける手法は記事風広告と言われるもので、特定の成分の効果などを紹介した情報欄の極めて近い部分に意図的に当該成分を含有する製品の広告をする手法は、当該情報を含んだ一つの広告とみなされることがあるという見解になっています。
さらに東京都では、新聞で連日広告を打ち、1日目では成分の訴求、そして2日目にはその成分を含む広告をする手法をとった場合、それぞれは医薬品医療機器等法(旧薬事法)の違反とは言えませんが、全体として1つの広告として判断し違反になるという見解を出しています。
健康雑誌はどう判断されるのか
書店などで販売されている健康雑誌をみてみると、『●●特集』と評してある成分の特集記事などが組まれていて、それと同時に他のページにその成分を含んだ商品の広告がでていたりします。
こうした場合の判断はどうなるのでしょうか。
この場合は、はやり特集コンテンツと商品広告との距離、さらにコンテンツの記事に関する学術性の高さ、メーカーのかかわり方などが問題になってきます。
個人的に言えば、学術的に正しいことであれば、消費者の知識が深まるものであり、健康雑誌が法違反を助長する『悪』と考えるのは早計です。
むしろ、いろいろな健康成分の知識を消費者に広めるということからすれば、エビデンスがしっかりしていさえすれば、むしろ歓迎すべきことではないでしょうか。
一方で、商品を広告する広告主については、行政サイドの人間がよく言うことですが、そんなに機能や効能を標ぼうしたいのであれば、医薬品として承認を取得するなり、特定保健用食品や機能性食品として許可や届け出をすべきだということになります。
確かに、その通りです。