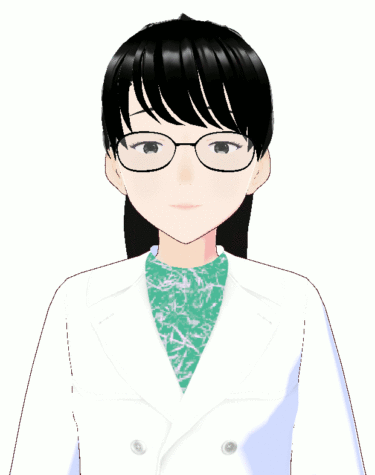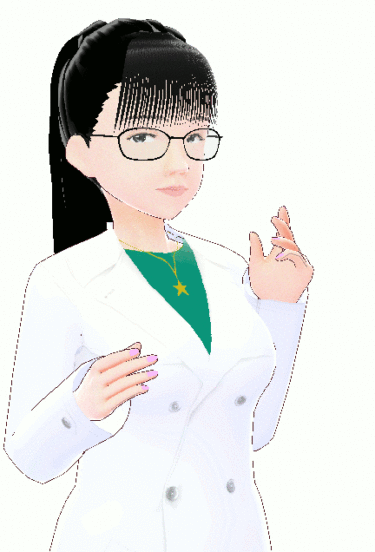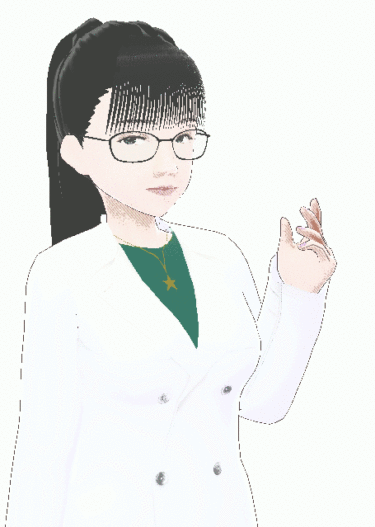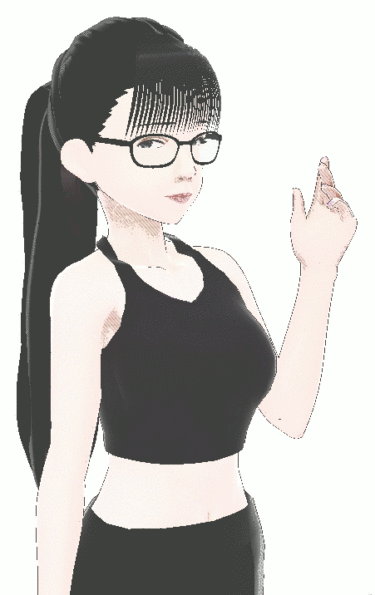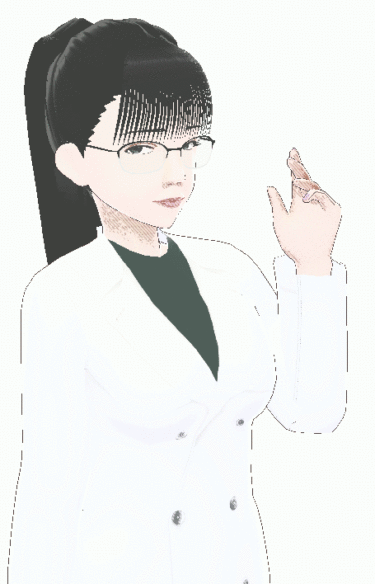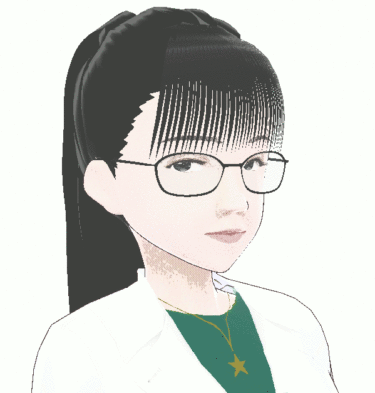ハロウィンといえばカボチャですが、ハロウィンの元になったケルト人の収穫祭ではカブが用いられていました。
これがアメリカに伝わった際に、カブにはなじみがなかったため、収穫祭の時期に多く収穫されていたカボチャが代用されるようになったのです。
ちなみに、カボチャは、ポルトガル語が由来で、カンボジアが訛ってカボチャになりました。
また南蛮からやってきた瓜ということで南瓜と書くようになったようです。
カボチャは英語で何て言う?
さて、カボチャは英語で何というでしょうか?
多くの人がパンプキンと答えると思います。
間違いではないのですが、日本のスーパーなどで売られていて一般に食卓にあがってくるカボチャは、パンプキンではなく、『スクワッシュ』になります。
英語では、カボチャのことを総称して『squash:スクワッシュ』といいます。
パンプキンは、ハロウィンで使われるオレンジ色の果皮のポポカボチャのことを指しています。
ハロウィンだけじゃない、カボチャの活躍の場
カボチャといえば、ハロウィンを連想する人は確かに多いのですが、冬至にカボチャを食べる風習もあります。
カボチャは長期保存ができ、免疫力を高めるビタミンEやβ‐カロテンが豊富に含まれていることから、冬場の貴重な栄養源だったことから、江戸時代に冬至にカボチャを食べる風習ができたと考えられています。
カボチャの皮もワタも種も有効活用

カボチャの実の部分は、抗酸化ビタミンであるビタミンEやβ‐カロテンが豊富に含まれているのですが、実以外の皮やワタには、実よりも多くのβ‐カロテンが含まれています。
ワタに関しては、食物繊維もたっぷり含まれていて甘みも強くなっています。
カボチャのワタは、ミキサーにかけてポタージュなどにしたり、細くカットしてスクランブルエッグなどに混ぜたりしても美味しくいただけます。
カボチャの皮は、細切りにしてきんぴらのようにして食べるのがおススメです。
カボチャの種には、リノール酸やオレイン酸が豊富に含まれているほか、ビタミンB2やビタミンEも多く含まれていて、アンチエイジング効果や、動脈硬化の予防も期待できま
す。
さらにカボチャの種は、リグナンも豊富に含み、女性ホルモン様の働きがあり、骨粗鬆症の予防効果も期待できます。
カボチャの種は、よく洗い、ぬめりを落として1日天日干ししてから、フライパンでよく炒って、焼き色がついたらよく冷ましてから、キッチンバサミで先端をカットして、中の緑色の部分を取り出して食べますが、市販されているものがあるので、それを利用するとよいでしょう。
カボチャの種は、1日10~15粒を目安に食べるとよいでしょう。