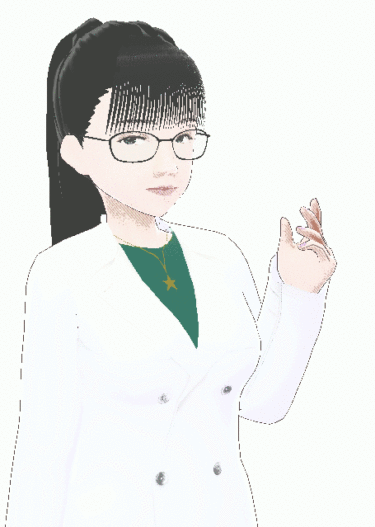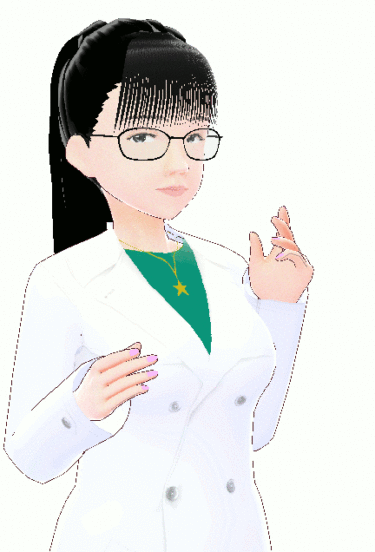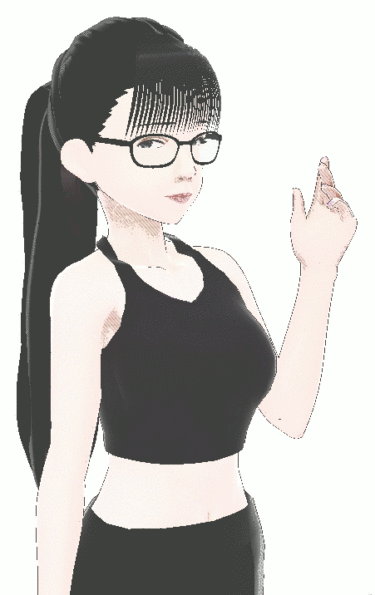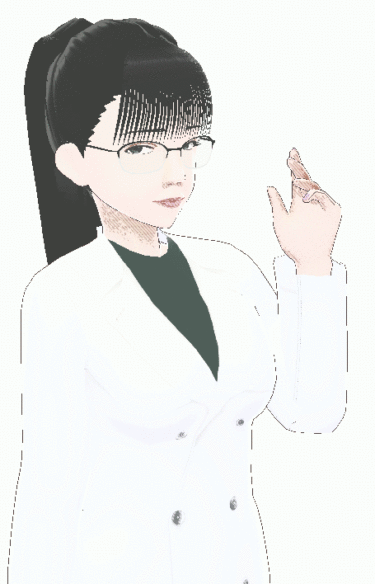蕎麦の原産地は東アジア北部から中国南部にかけてで、そこから東アジアやインド北部へと伝わっていき、ヨーロッパでも15世紀ごろから栽培が始まっています。
日本での栽培歴は古く、縄文時代後期から弥生時代あたりではないかと言われています。
奈良時代には種子を蕎麦めしやお粥にして食べていたと言われていて、蕎麦切り、つまり現代の麺類として蕎麦が食べられるようになったのは意外にも歴史が浅く江戸時代中期になってからとされています。
蕎麦は、タデ科のソバ属に属していて、非常に重宝な食物で、やせた土地や寒冷地でも十分に育つことができ、わずか2ヵ月ほどで収穫できます。
特に晩夏から10月頃に収穫される秋蕎麦は、香り・味わいともに優れていて新蕎麦として珍重されます。
蕎麦の栄養成分
蕎麦の栄養成分をみてみると、蕎麦殻にはポリフェノールの一種であるルチンが多く含まれていて、毛細血管の強化や血糖値やコレステロール値を下げる働きも期待されています。
さらにこのルチンは、ビタミンCの吸収を助けて、コラーゲンの生成を高めることによる美肌効果も期待されています。
蕎麦には意外にも蛋白質が多く含まれていて、成分の約13%は蛋白質で、コレステロールを減らし、体脂肪の蓄積を防ぐ働きがあるとされています。
アミノ酸のリジンも多く含まれるため、組織修復効果も期待されています。
その他、蕎麦には血圧上昇を誘発するアンギオテンシンⅠ変換酵素の働きを阻害して、高血圧の予防につながるアンギオテンシンⅠ変換酵素阻害因子や、脳内コリン濃度を高めて記憶力の向上につながる脳機能維持改善に役立つコリンなども多く含まれています。
さらにビタミンB1、ビタミンB2、パントテン酸、ナイアシン、カリウム、食物繊維などが多く含まれています。
ただし、蕎麦はアレルゲンとしても知られていて、時に生命に関わる重篤な反応も起こりうることもあるので、注意が必要です。

日本の蕎麦事情
蕎麦というと、信州そばなどを連想する人もいますが、日本では蕎麦の生産地は、北海道が大産地になっています。
しかし、国内で消費しているそば粉の約8割は輸入品になっていて、その8割以上は中国産になっています。
そば粉は、製粉の度合いやふるいの加減で分類されています。
『一番粉』は、胚乳の中心部分だけをひいたもので、真っ白で最上級品になっていますが、香や風味は弱くなっています。
『二番粉』は、胚乳と胚芽の一部をひいたもので、薄黄緑色をしていて香りも風味も豊かになっています。
『三番粉』は、胚乳の一部と胚芽と種皮をひいたもので、暗い青緑色をしていて栄養豊富で、香は良いものの風味は弱くなっています。
『末粉』は、胚芽と種皮をひいたもので、黒っぽく多くの破片が混入していて、食感は劣るので、そばがきや菓子、乾麺の色付けなどに用いられますが、栄養価と風味は高くなっています
年越し蕎麦
年越し蕎麦は英語で何というかというと、「buckwheat new years eve」になりますが、その歴史は鎌倉時代からはじまっています。
鎌倉時代、博多のお寺で年を越せないほど貧しい人々に、蕎麦粉で作った蕎麦餅がふるまわれたのですが、その蕎麦餅を食べた人達の運気が翌年から上がったという噂が広まったのが始まりと言われています。
年越し蕎麦には、蕎麦のように細く長く過ごせるということから長生きできるようにとの願いが込められていて、また蕎麦は切れやすいことから、今年の不運を切り捨てて、来年を幸運で迎えられますようにという願いも込められています。
蕎麦は風雨にさらされても、日光を浴びると再び元気になる生命力があることから、来年の無病息災を願うという意味もあるそうです。