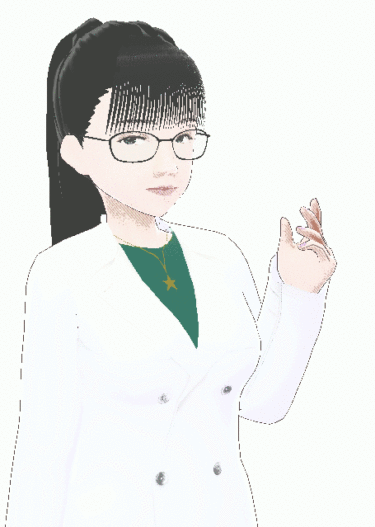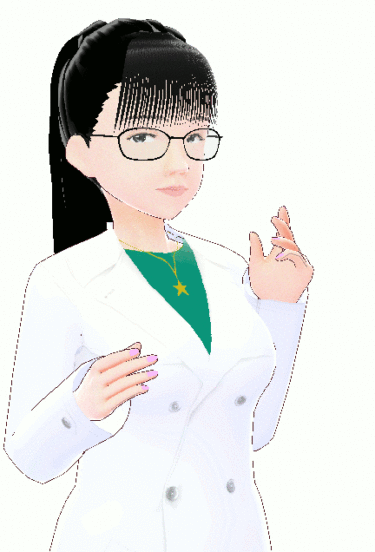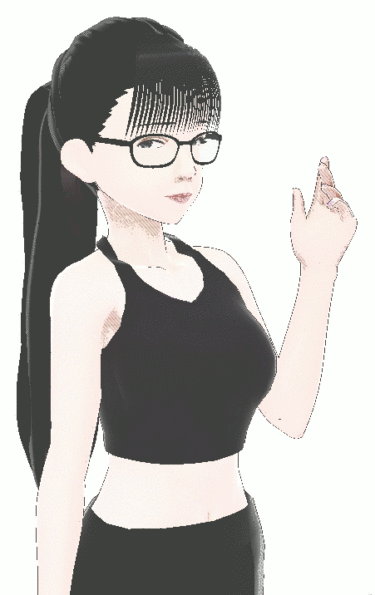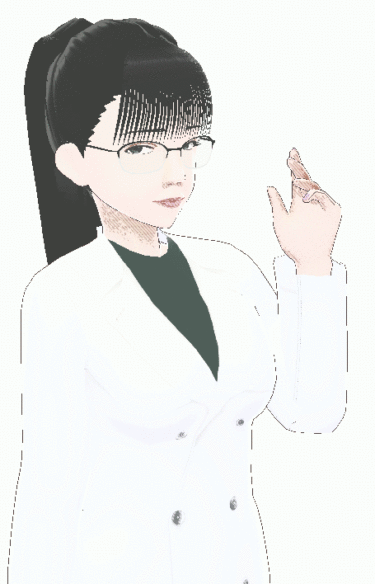栄養の摂り方は、歳とともに変わっていき、留意しなければならない点も変化してきます。
乳幼児期の栄養の摂り方
生まれたての赤ちゃんは、もちろんお母さんの母乳や人工乳などミルクを吸うということしかできませんが、次第に離乳食へと移っていきます。
生まれたから数カ月は、ものを咀嚼することはできず、哺乳反射によってミルクを吸うというレベルになります。
しかし数カ月経つと離乳期を迎え、1~2歳になると自分で食べれるようになります。
5歳ぐらいまでは、障害の食習慣の基礎を身につける時期で、主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い献立が大切になってきます。
子供の活動量や食欲に合わせて間食なども取り入れると良いでしょう。

学童期・思春期の栄養の摂り方
子供が小学校に通うころになると、食習慣が確率してきて、味覚も豊かになってきます。
成長期なので、丈夫な骨をつくるためのカルシウムや筋肉を作るためにタンパク質など、体を構成する栄養素を過不足なく補うことが大事になってきます。
生活リズムの乱れは健康によくないですし、食習慣にも悪影響を及ぼすので、小学生のうちから規則正しい生活習慣のクセをつけておくことも重要です。
さらに中学生、高校生となるに従い、体も子供から大人へと大きく成長し変化してきます。
この時期は骨量が最も増える時期なので、カルシウムをはじめとした栄養素をきちんと摂ることが重要です。
大人の栄養の摂り方
二十歳になり成人してくると、成長もしだいにゆるやかになってきて、中高年にもなると基礎代謝が落ちてきて、食べ過ぎによる肥満や生活習慣病に注意する必要が出てきます。
社会に出るようになると、生活習慣が乱れやすくなったり、ストレスをためやすくなることで疲労しがちになりますので、ストレス対策をすることも重要になってきます。
栄養バランスの偏りに注意をしていく必要があり、基本は主食・主菜・副菜がそろった食事をすると良いでしょう。
どうしても外食中心になってしまうという人も、主食・主菜・副菜ということをしっかりと頭に入れて栄養バランスをとるように心がけましょう。
また更年期の女性は、ホルモンバランスが乱れやすいので、それを改善する大豆製品をしっかり摂ることがオススメです。
高齢者の栄養の摂り方
高齢者は、生理機能の低下に伴って若い時と比べて低栄養状態になりやすいので注意が必要です。
高齢になると活動量が減ってくるので、食欲も減退してきて、食事の量も減りがちになります。
量は少なくなても、必要なエネルギーと栄養素をしっかりと摂取することが大切です。
盛りつけを変えてみるとか、彩りを工夫してみるとか、食欲をわかせるような工夫をしてみても良いかもしれません。
また消化機能や吸収機能が低下してきているので、よく噛んで唾液の分泌を増やすようにすると良いでしょう。