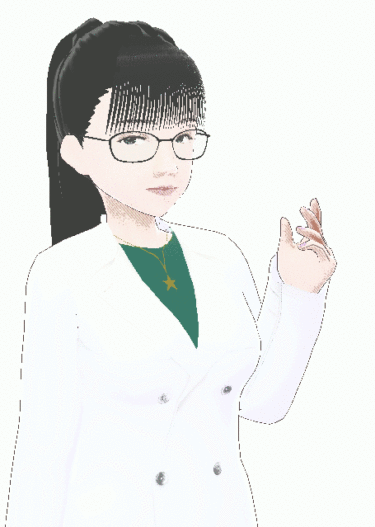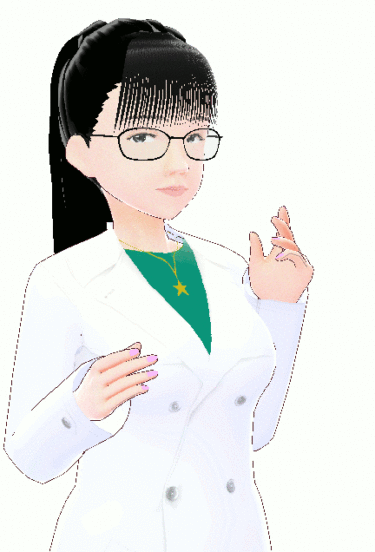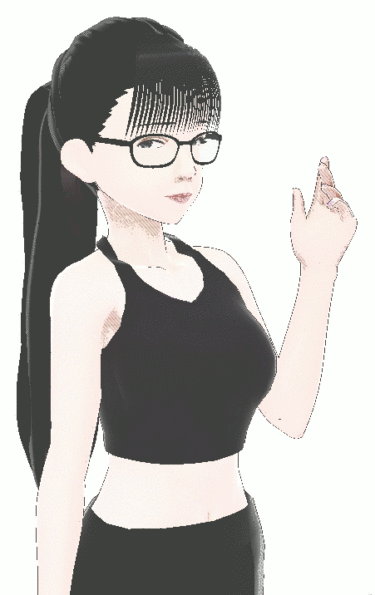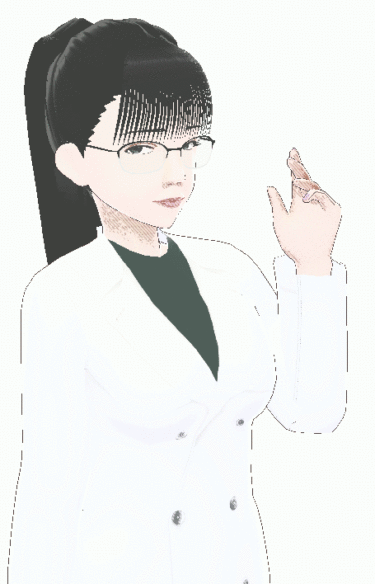脳がない生物にミミズがあります。でもミミズは完成された生物です。
脳がないのに、夜と昼の光の強弱を判断し、条件がそろえば地中から地表へ出てきます。
落ちている葉や小枝が食べられるかどうかも判断しています。
このように腸は脳よりもはるか前にできていて、腸がなるべく効率よくエサをGETしてエネルギーを取り込んでいけるための作戦室として、脳が発達していきました。
腸は判断している
食べ物の中に、食中毒菌が混入した食べ物があった場合、まず脳が見た目で判断します。
しかし見た目では変化がわからない場合は、それを普通と判断し口にしてしまうという判断を脳は下します。
口にしてしまった場合、やがて胃腸へ入っていきます。
食中毒菌が混入した食べ物が腸に入ってくると、腸は「これは入れちゃダメなもの」と判断をして拒絶反応が起き、これが嘔吐や下痢となり体外へ排出しようとします。
つまり、脳で判断できなかったものを腸はしっかりと判断して体を守っているということになります。
自分自身で考え動く腸

多くの組織は、脳からの指令を受けて動いていますが、腸は独自の判断で動いている部分があります。
その代表例としてあげられるのが、脳死になった場合でも、腸はひとりで機能し続けることができます。
一方、腸が完全に死んでしまうと、脳の働きも完全にストップしてしまうのです。
腸がよく第二の脳と言われる所以とは
腸はよく『第二の脳』という言われ方をしたりします。
これは、人間の腸内には、約1億個の神経細胞があって、網目状の神経ネットワークが築かれているからです。
腸の神経細胞は、その数はさすがに脳のそれにはかないませんが、腸内の神経ネットワークには思考や情動に影響をもたらす多くの情報がやり取りされています。
それに一役かっているのが腸内細菌であると言われています。
さらに、腸はドーパミンやセロトニンといった幸せホルモンと言われるものを生産しています。
腸が元気で、ドーパミンやセロトニンが多く作られていれば、心も明るくポジティブで幸福感に満ちてきますし、逆に腸の調子が悪くなると、心が暗くネガティブになってきてしまいます。
ある意味、腸は心の健康に深く関係していると言えます。
体思いの腸
腸は、非常に体思いなのです。
例えば、食べ過ぎや飲みすぎ、タバコに関しても、食べたい、飲みたい、吸いたいという欲求に勝てず、生活を乱してしまう原因にもなります。
しかし腸は、体に悪いものが入ってきたり、よくない状態が続くと、便秘になったり下痢になったりして不調を訴えます。
腸内には多くの腸内細菌がいますが、腸の調子が悪くなり心身が弱ってしまうことは、人間だけでなく腸内細菌にとっても都合が悪いことともいえるでしょう。
腸には、確かに難しい計算問題をしたり、言葉や文章を記憶したり、何かを表現したり、哲学的な問題を考えるといった知能はありませんが、体のことを思い、いろいろと考えていると言えるのです。