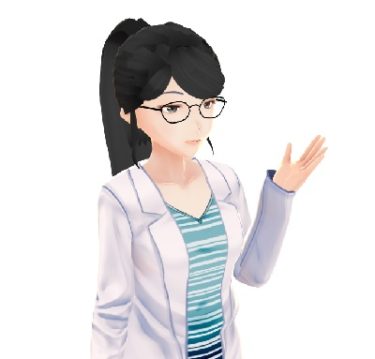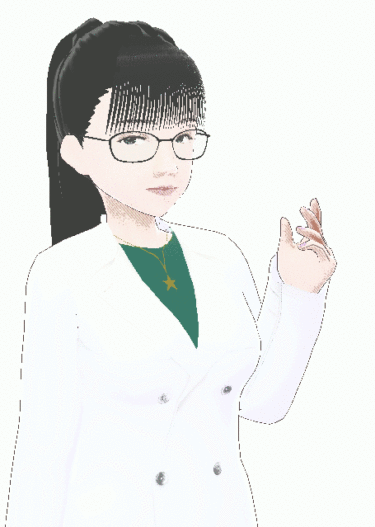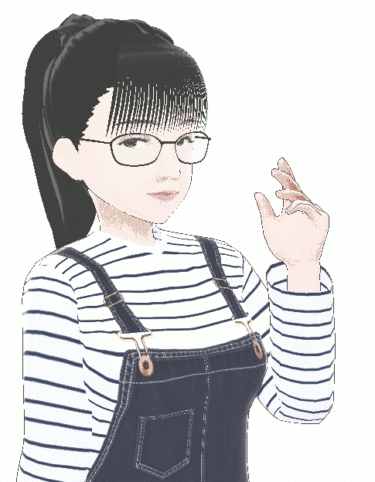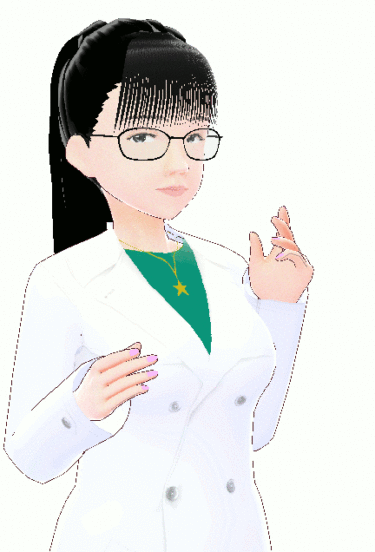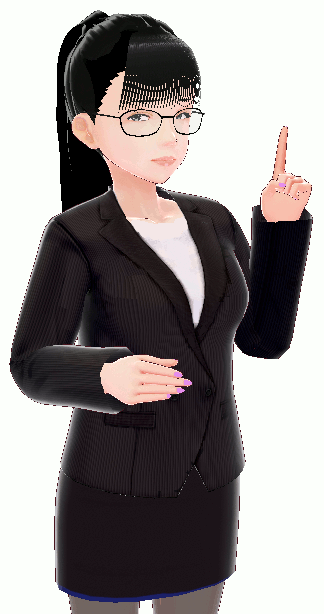『偏差値』は、ある集団において、自分の学力が平均からどのぐらい離れているかの指標となります。
偏差値の意義
テストの点数で学力を判断しようとすると、試験によって問題の難易度が変わってきてしまいますので、学力を直接測る指標としては不適切です。
例えば、あるテストで60点を取った学生がいるとします。
しかし、その学生はもっとやさしいテスト問題だったら80点を取ったでしょうし、もっと難しいテスト問題だったら40点しか取れなかったかもしれません。
そうすると学力が同じ同一人物なのに、点数に幅ができてしまいます。
従って、同じテストを受けた集団の中で、平均からどのぐらい悪かったのか、平均からどのぐらい良かったのかを出す必要があります。
それじゃ、平均点より20点高かった、平均点より20点悪かったというように、平均点との点差で考えればいいじゃないかと思うかもしれませんが、これも違います。
なぜならば、各受験生の点数のバラつきも考慮しなければなりません。
例えば、すごく簡単なテストで平均点が80点のテストで90点取った場合と、すごく難しいテストで平均点が10点のテストで、ほとんどの人が0点だったところを20点取ったのでは、その評価が違うからです。
そこで偏差値が用いられるのです。
偏差値の計算法
偏差値は、各生徒の点数、テストを受けた人の平均点、標準偏差と呼ばれる点数のばらつきから求められます。
標準偏差は、(各生徒が取った点数ー平均点)の二乗の総和を出し、それを生徒の数で割り、その平方根になります。
偏差値は、(各生徒が取った点数ー平均点)を標準偏差で割り、10をかけてから50を足します。
偏差値が100なんてことはありうるのか

偏差値というと、50より上だと平均より良く、下だと平均より悪く、25~75の間というイメージを持っている人も多くいると思います。
しかしこれは大きな誤解です。
結論から先にいうと、偏差値は100を超えることもありますし、マイナスになることだったあるのです。
だいたい全国模試などをやっても、成績が良い生徒でもせいぜい偏差値75ぐらいということになります。
それでは、偏差値が100なんてことはありうるのかというと、可能性としては十分ありえます。
模試などでは、各生徒の学力をみるために、平均点が60点ぐらいでほどよくばらつくような問題になっているので、だいたいほとんどの人が偏差値25~75の間に収まるように設計されているものです。
しかし、もし難しいテストが出され、半数近くの人が0点、そして残り半分の人が10点、そんな中、あなただけ50点取ったとします。
このような場合は、あなたの偏差値は100を超えてきます。
このように受験生のテンスのばらつき・分布が極端な形となった場合、つまり平均点が非常に低く、多くの人が低い点数の中、一人だけ高得点を取ったりすると、偏差値は100を平気で超えます。
この逆に、平均点が90点、ほとんどの人が80点以上のテストで一人だけ0点を取ったりすると、マイナスの値が出たりすることもあるのです。