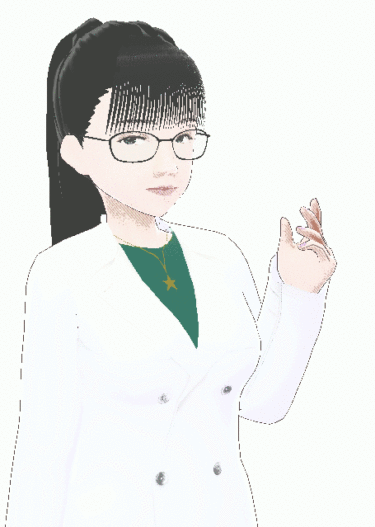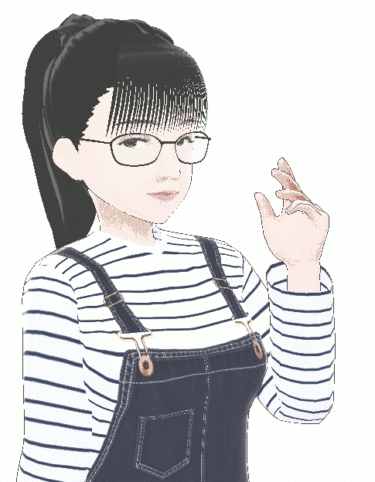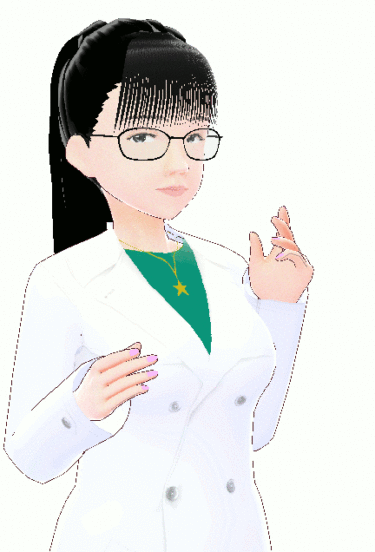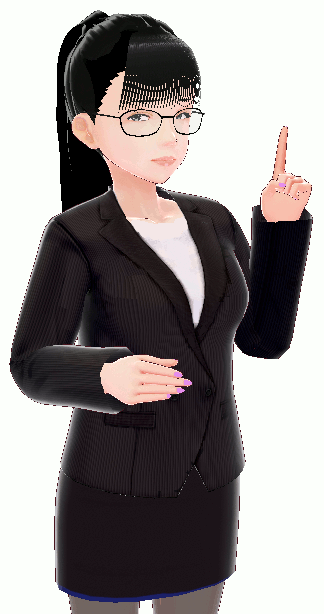公共のルールなのに、その命令に逆らって言うことをきかない人がたまにいます。
どうでもいいことならいいのですが、周りの人に迷惑がかかるようなことだと、本当に社会のゴミ、低能人間などと思いたくもなってしまいます。
しかし、こうした行為ももしかしたら、人間の心理からきているのかもしれないのです。
カリギュラ効果とは
心理学的には、人間というものは、他人から命令されたり禁止されたりすると、ストレスを感じてそれを破りたくなるものなのです。
鶴の恩返しではないですが、「絶対に見ないで」と言われれば、逆に見たくなってしまうものです。
「これ、絶対にヒミツだからね」と言われれば、逆に誰かに話したくなったという経験がある人も少なくないのではないでしょうか。
会社で部下を育てるときも、『気づき』というものが重視されます。
そんなの答えがわかっているなら、そんな気づかせるんじゃなくて、直接正解となる方法を教えて、こうしなさいと命令すれば早いし、効率的だと思うかもしれませんが、他人から答えを与えられるよりも、自分で気づいたときのほうが、自分の成長にもつながりますし、素直にそれを受け入れることができるのです。
人間は本来、自分のことは自分で決めて、自由に行動したいという欲求を持っているものなのです。
したがって、他人から命令されたり禁止されたりすると、それをストレスに感じ、破りたくなってしまうのです。
こうした人間の心理を、『カリギュラ効果』と言ったりします。
ポイ捨てとカリギュラ効果

街を歩いていると、「ゴミを捨てるな!」と注意書きがあるそばに大量のゴミが捨てられているようなケースもあります。
こうした時に役立つのあが『ナッジ』と呼ばれる行動心理です。
『ナッジ』とは、人間が望ましい行動を取れるように後押し、誘導するアプローチです。
ナッジは、肘でそっと押すというような意味の言葉で、命令で上から強制するのではなく、あくまでも自発的にその人にとって望まし行動に誘導していくという手法で、実社会の中でもいろいろと応用されています。
オランダのスキポール空港のトイレには、男性用の小便用の便器に、小さなハエの絵が描かれています。
男性は用を足すときに、無意識にこのハエを目標にします。
こうした結果、トイレの飛散による汚れは80%も減少し、清掃コストも20%削減できたようです。
ゴミのポイ捨てにしても、コミ箱にバスケットをつけることで、そこにシュートしたくなり、ポイ捨て防止につながります。
カリギュラ効果の応用
カリギュラ効果も、社会的な応用例があります。
例えば、「本日限定」とか「有料会員限定」といったものです。
制限することで、集客力を高めたり、会員登録者数を増やしたりするのも一つの手法です。