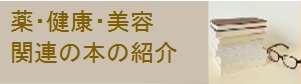薬剤師レジデントマニュアル
1~2年目の薬剤師さんに向けた薬剤師との知識と臨床の現場を結びつける一冊です。
白衣のポケットにも入るコンパクトサイズにも関わらず、充実した中身の新人薬剤師のための必須医療マニュアルです。
信頼と実績のある神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部の実力派メンバー達が執筆していて、循環器疾患、消化器疾患、がんなど主要52疾患について、簡潔にポイントをおさえてまとめられていて、次のようにまとめられ解説されています。
- 患者の状態把握
- 治療(標準的処方例)
- 薬剤師による薬学的ケア
- 処方提案のポイント
調剤業務はもちろんのこと、検査、フィジカルアセスメントなどの業務について記載があります。
処方をチェックするポイントや服薬指導・副作用モニタリングについての説明もわかりやすくされています。
付録も充実しています。
- これまでに発出された緊急安全性情報,安全性速報
- 重篤副作用疾患別対応マニュアル・疾患リスト
- 腎機能低下時に注意の必要な薬剤投与量一覧
- 妊婦・授乳婦への薬物投与
- わが国における薬剤師レジデント制度
疾患の理解と薬の関係を理解するのにオススメです。
実践 小児薬用量ガイド
小児用量の計算は、児童の体重によっても変わってきたりするので調剤の中でも手間がかかります。
実際に臨床現場では、処方箋に記載されてきた用法が添付文書やインタビューフォームに記載されている内容と異なっていたりする場合があります。
特に小児用量については、添付文書を見ただけでそのまま解決できないケースも多くあります。
『実践 小児薬用量ガイド』では、体重kgあたりの小児薬用量をまとめてあり、漢方薬や外用薬に関しても網羅されているため、これ一冊で小児科領域の用法に関して自信を持つことができるようになります。
小児科領域の小児用量をチェックするのに非常に便利で、臨床現場の薬剤師の間からも高い評価を得ている本です。
白衣のポケットにも入るサイズで、持ち歩くのにも便利で、現場でも手軽に活用することができます。
薬効別 服薬指導マニュアル
きちんと処方監査ができ、正確に調剤ができたとしても、実際に服薬指導において患者へ説明するというアウトプットの部分がうまくいかないと、患者の誤用にもつながってしまいます。
特に1~2年目の薬剤師の場合は、はじめて服薬指導する薬も多く、勉強することも多いと思いますが、疾患名からでも薬品からでも検索する事ができ、知らない薬、はじめての薬について説明するときに心強い味方になってくれる本です。
本書のイチオシポイントは、何といっても指導ポイントの部分で、薬剤師向けに作用機序等もおさえて丁寧に説明してあることに加え、患者さん向けの説明文が載っていて、実際に患者さんに向けてかみ砕いたわかりやすい文章になっているので非常に参考になる点です。
また、調剤薬局ではジェネリックも含め数百から数千の薬を扱っていますが、レアな処方などだと長年薬剤師をやっていてもなかなか調剤する機会がないといったものもあり、こういった時にも力を発揮してくれる一冊です。
特に、処方箋枚数が多く、取り扱っている薬も業務量も多くスピーディに仕事をこなしていかなければならない人にとっては非常に重宝する一冊になります。
薬剤師のための医学論文の読み方・使い方
一歩上の薬剤師を目指したいというときに、勉強会に出席したり、医学論文を読んだりするときに、臨床データを読み解き考察する力というのが非常に大切になってきます。
またEBM(Evidence based medicine)つまり臨床論文において、医師の経験や主観だけではなく根拠のあるデータに基づいた医療という考え方が重視されるようになってきている中、ますます医学論文・臨床論文におけるデータを読み解く力が必要になってきます。
製薬メーカーのパンフレットなどは、もちろんウソはないですが、自社の製品をよりアピールするような傾向にあるので、示されたデータから客観的に判断する力も必要になってきます。
試験デザイン、P値、ハザード比、オッズ比、95%信頼区間、クロスオーバー、サブグループ解析など医学論文を読むにあたって必要となってくる統計学的用語を非常にわかりやすく解説しているので、医学論文を読むための統計的知識を学びたい人にとっては最適の一冊です。
現場で役に立つ内容になっていてPubMed検索のコツなどについても説明されているので、自分で論文を調べ、それを客観的に判断していく力がついていく本です。