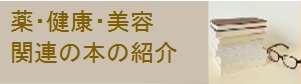薬理学
疾病の成り立ちと回復の促進 薬理学 第3版
●第1部「薬理学総論」では、薬理学の基礎的な知識をわかりやすくまとめてあり、医薬品(麻薬)の管理などについても解説があります。
●第2部「薬理学各論」では、疾患・病態の概略、薬物の作用機序、代表薬などについて簡潔に述べ、成人看護学の各分野との有機的なつながりを意識した組み立てになっています。
●それぞれの薬物について、投与経路や有害作用、禁忌などの覚えておくべき特徴が目にとまりやすいようにまとめられています。
●薬理作用のみならず、「投与時の看護のポイント」などについても記述しており、臨床で活用が可能な内容となっています。
●カラーの図により、「薬の効くメカニズム」が理解しやすくなっています。
第1部 薬理学総論
第1章 薬理学を学ぶにあたって
第2章 薬理学の基礎知識
薬力学・薬物動態学・薬物相互作用・薬効の個人差に影響する因子・薬物使用の有益性と危険性・薬と法律
第2部 薬理学各論
第1章 抗感染症薬
第2章 抗がん薬
第3章 免疫治療薬
第4章 抗アレルギー薬・抗炎症薬
第5章 末梢での神経活動に作用する薬物
第6章 中枢神経系に作用する薬物
第7章 心臓・血管系に作用する薬物
第8章 呼吸器・消化器・生殖器系に作用する薬物
第9章 物質代謝に作用する薬物
第10章 皮膚科用薬・眼科用薬
第11章 救急の際に使用される薬物
第12章 漢方薬
第13章 消毒薬
付章 輸液製剤・輸血剤
付録 看護業務に必要な薬の知識
薬理学のバイブル。
薬物遺伝学や癌の標的治療など最新の情報が豊富に盛り込まれています。
薬理学と他の分野を関連させ、薬物治療の基礎と臨床を詳しい解説しています。
THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS, 12th ed.
「薬の作用様式と作用機序」についての基本原理、「生体内情報伝達システム」について、生命科学の進歩に合わせわかりやすく解説をしています。
患者ごとに違う治療効果・副作用(薬物反応性)を踏まえ、患者に適した薬の種類の選択と投与量・投与方法の選択といういわゆる個別化医療(personalized medicine)が重要視されてきている中、薬理遺伝学(薬理ゲノミクス)や薬物トランスポーターについて詳述しています。
ハーバード大学医学部の学生と教官の共同作業により作成された画期的な臨床薬理学のテキストになっています。
非常に分量が多く、臨床との関連性を強調しながら解説している点に現代の医学教育を垣間見ることができる。生理学からの流れを重視し、薬の作用機序に重点を置いているため理解しやすい作りとなっています。
簡明なイラストを豊富に用いて各病態のメカニズムを生化学・生理学・病態生理学に基づいて整理していて、個々の薬物が標的とする分子機序が明にされています。
具体的な症例を軸に臨床現場でのより良い薬物選択を学ぶように作れれています。