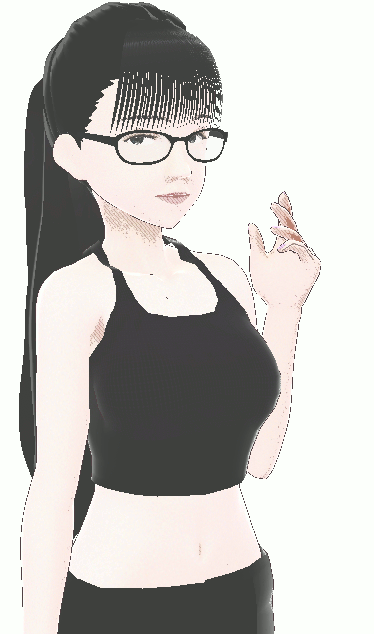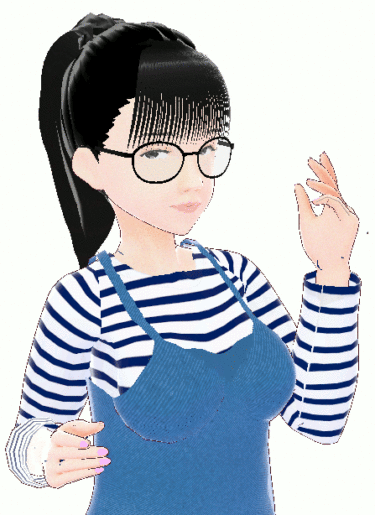ジャスミンというと、杏里さんの『オリビアを聴きながら』を連想する人もいるかと思います。
♪ジャスミン茶は、眠り誘う薬~ というように、その心地よい香りで眠りを誘うということで、ジャスミンの香りはとてもいい香りというイメージがあると思いますし、実際にそうです。
ジャスミンの香りの成分は
ジャスミンは、漢字で書くと耶悉茗となりますが、アジアからアフリカの熱帯から亜熱帯の地域を原産とするモクセイ科ソケイ属の植物の総称を指します。
ソケイ属の植物は約300種ほどが確認されていますが、その中でいくつかの種では花に強い芳香があることから、香水やジャスミン茶の原料として用いられています。
ジャスミンは、香水としても用いられていますが、香料の原料としてはフランスのグラースで16世紀の中頃から大規模に栽培されるようになっていきました。
ジャスミンの花は夜に咲くため、花が開ききった明け方に摘み、有機溶媒で抽出して、コンクリートと呼ばれるワックス状の芳香をもつ固体が得られますが、香料として使われている『ジャスミン・アブソリュート(ジャスミン抽出物)』は、このコンクリートをさらにエタノールで再度抽出したものになります。
しかし、『ジャスミン・アブソリュート』は、アレルゲン陽性率が高い香料なので、注意が必要です。
ジャスミンの花には香りの成分が豊富に含まれていますが、その中でも特徴的なのが、『cis-ジャスモン』という成分で、工業的に生産する方法が確立していないため、自然の鼻からの抽出精製となり、非常に高価になってしまいます。
ソケイ属の主な香気成分は、ジャシモン酸メチルで、こちらの系統の香料は、工業的生産もできるため、安価で香水やアロマオイルなどに多く使われています。

ジャスミンとインドール
インドールと聞くと、おならの悪臭成分、うんちの臭い成分と連想する人もいると思いますが正解です。
おならやうんちの悪臭は、インドールやスカトールなのです。
このインドールが、どう香りのよいジャスミンと結びつくのかというと、ここで、もう一つ別の植物を出さないといけません。
それが、クチナシです。
クチナシはアカネ科の植物で、独特な形の赤黄色の果実をつける常緑低木の植物で、その果実は山梔子という漢方生薬にも用いられています。
このクチナシの学名が、なんと Cardenia jasminoides なのです。
どういう意味かというと、「ジャスミンのような」という意味の学名です。
クチナシはアカネ科、ジャスミンはモクセイ科ソケイ属と植物の分類学的にも違うもので、近縁でもなんでもありません。
クチナシの香りは、リナロールや酢酸ベンジルといった香気成分によるものですが、クチナシはもちろん、ジャスミンにもインドールが含まれています。
薄まればいい香り
悪臭の代表格のように言われているインドールですが、ジャスミンにも含まれています。
しかし、希釈され低濃度となると、新鮮な花の甘い香りとして感じられるのです。
同じ成分でも、その空気中の濃度によって、違った感覚を与えるものなのです。
「におい」という字を感じで書くと、「匂い」であったり「臭い」となります。
「匂い」ならば良い香り、「臭い」ならば悪臭となり別の読み方をすれば「くさい」になってしまいます。
このように、芳香と悪臭は紙一重なのかもしれません。