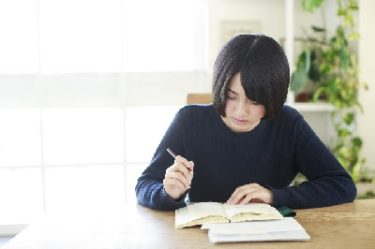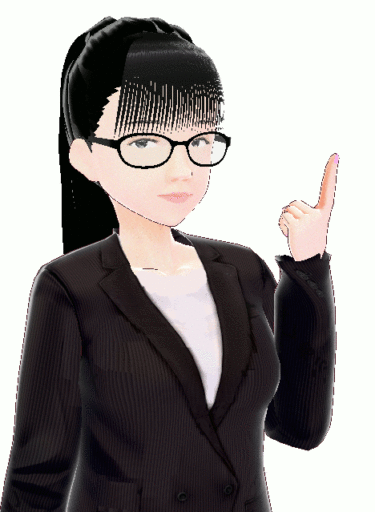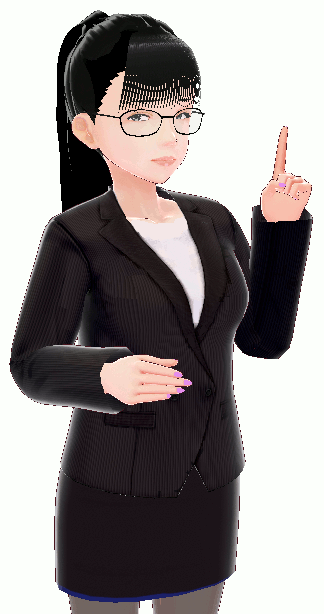勉強や仕事の効率を上げるためのちょっとしたコツを3つほどご紹介します。
やる気がおきないときはスモールステップ
勉強でも、仕事でもやる気が起きないというときがあると思います。
そういったときは、『スモールステップ』から始めることがオススメです。
『スモールステップ』、つまりとりあえずの最初の小さな一歩です。
勉強をするにしても、たとえやる気がなかったとしてもとりあえず参考書を開いてみるのです。
仕事のやる気がでない時でも、とりあえずパソコンを立ち上げてみるのです。
人間は、何かの行動を始めることで、その行動が続くようにできていて、始めると今度は、やめるほうが難しくなるものなのです。
このような脳の働きは作業性興奮と言われていて、集中しようと無理矢理に追い込むことをしなくても、とりあえずやり始めるのです。
そうすれば、いつの間にか集中しているものなのです。
例えば、苦手な作用などをどうもやる気にならないことがありますが、ちょっとだけ初めてしまえば、脳の線条体が活動し始めて、作業することが快感にすらなってくるものなのです。
ToDoリストで脳に余裕を
勉強や仕事を始めようとしても、何から手をつけたらいいかわからないといったことがあると思います。
どうしてそうなるのかというと、何をすべきなのかということを考えるのに脳のワーキングメモリを使ってしまっているからなのです。
脳のワーキングメモリが容量オーバーになると、集中できなくなり、勉強や仕事の質も下がってしまうのです。
そういうとき、ビジネスの研修でもよくでてくる『ToDoリスト』が有用です。
やるべきことをすべて書き出してみることで、頭の中の情報が整理されるので、ワーキングメモリにも余裕ができ勉強や仕事に集中できるようになります。

勉強をルーチン化する15分勉強法
15分勉強法は、15分単位で、勉強のスケジュールをパターン化する方法です。
人間は、集中した状態を保てるのは10~15分程度だと言われています。
そこで15分単位のスケージュールを立てて勉強するという方法です。
15分勉強法は、最初の15分にまず前日の復習をします。
そして15分ごとの時間割を作ります。
1科目につき30~60分の時間を決めて、前半は参考書を読み、後半は問題集を解きます。
最後の15分は、翌日の勉強の予定を立てます。
1科目60分を目安にスケジュールを組むとすると、最初の15分で前日の複数をします。
次の15分で、新しく学ぶ内容の解説を参考書で勉強します。
次の15分は、今日学習した内容の部分の問題を解く時間に当てます。
そして最後の15分は、答え合わせをしたり、翌日の学習の予定を立てたりします。
こうしたことをパターン化することで、集中力が維持できるようになるのです。