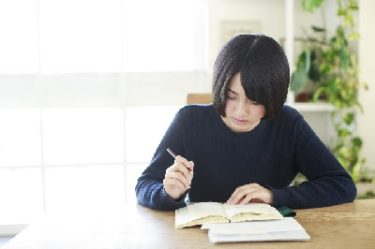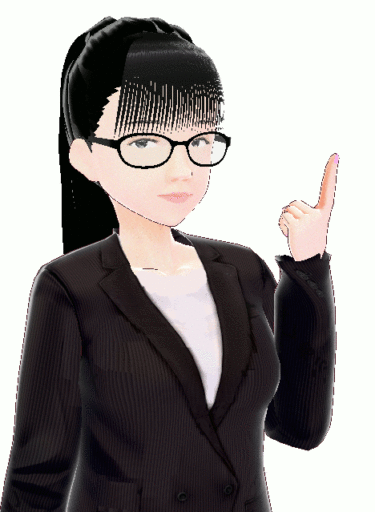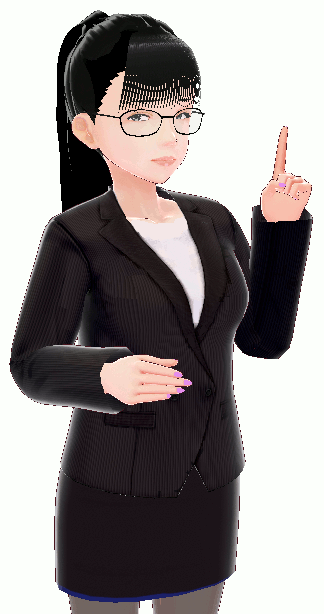言語は難しいもので、その国々の文化や発想の仕方が深くかかわってきます。
お隣の中国でもこんなに違う言葉
たとえば、日本のお隣の中国においても、だいぶ違ってきます。
日本で『汽車』というと、線路の上を走る蒸気機関車になりますが、中国では『汽車』というと自動車を意味します。
それでは中国では汽車のことを何というのかというと『火車』になります。
『火車』というと、日本語では台所事情が苦しい「火の車」を連想しますし、英語では消防自動車のことを「fire truck」といいます。
日本で、トイレに入って『手紙』でおしりを拭いたというと、相当の変わり者になってしまいますが、中国では『手紙』はトイレットペーパーのことになります。
それでは中国では『手紙』のことは何というのかというと、『信』になるそうです。
お隣の中国、しかも同じ漢字でも、意味が違ってくるというのは、その国々での文化や言語の発展の違いということで、なかなか興味あることです。
日本語から英語を推測すると大変なことに
たとえば、『小腸』は、小さいはsmall、腸は bowel や intestine なので、『小腸』は、small bowel や small intestine だろうということになりますが、これは正解です。
しかし、『花火』は、花の火なので、flower fire とやると意味が通じなくなってしまいます。英語で『花火』は、firework になります。「火の仕事」ですね。
同じように『火花』は、fire flower ではなく、spark になります。
『火山』は、fire mountain かというと、それは違って volcano になります。
面白いのが、『山火事』です。日本語から推測すると、mountain fire と言いたくなりますが、forest fire なのです。山火事なのに、森の火事なのです。
英語の have と make の発想
英語の動詞でもっとも重要なものといえば、be動詞とともに、do があげられるでしょう。
doは、「~をする」という意味で、その守備範囲というか用法はかなり幅広いものになりますが、いくら日本語が「~をする」だからといって、その全てを do で訳すことはできません。
状況によっては、have や make が使われます。

ここで、英語の考え方のポイントとして、次のようなこと言えます。
have は、楽しみながらすること、気楽にすることに対して用います。
おしゃべりをする ⇒ have a nice chat
一杯飲む ⇒ have a drink
ひと風呂浴びる ⇒ have a bathe
ぐっすり眠る ⇒ have a good sleep
これに対し、make は、努力が必要なことに対して用います。
演説をする ⇒ make a speech
生計を立てる ⇒ make a living
良い成績をとる ⇒ make good grades
決定する ⇒ make a decision
同じ「試みる」という場合でも、ちょっとトライしてみようかなという気楽な場合と、きちんと企画してそれに向かって努力しようという場合では表現が違ってきます。
ちょっとやってみるかという場合は、have a try と have を使いますが、
きちんと計画してやろうという場合は、make an attempt になります。
こうした形で、have と make という単語を眺めてみるのも面白いかもしれません。