まず『思考』とは何ぞやということになりますが、専門的には『思考』とは、知覚や表象、イメージから与えられた材料を統合し、対象の本質や相互の関連を把握して、概念を形成して、判断や推理を行う精神機能になります。
思考は主に言語を用いて表現され、『思考の流れ』・『思考形式』・『思考内容』の3つの側面があります。
そして思考が言語を用いて表現されることから、思考の評価は会話を通して可能になってきます。
思考の3つの側面
思考の3つの側面、つまり思考に異常がないかどうかを判断するときに、次の3つの側面で判断されていきます。
『思考の流れ』は、思考が継続的にどのように進んでいくかということで、それが早いか遅いかが判断されます。
思考の流れをみるときには、その内容は考慮しません。
『思考形式』は、叙述の1つの部分が次の部分にどれだけ合理的に結びついているかがみられます。
『思考内容』は、会話の内容そのものになります。
思考の異常パターン
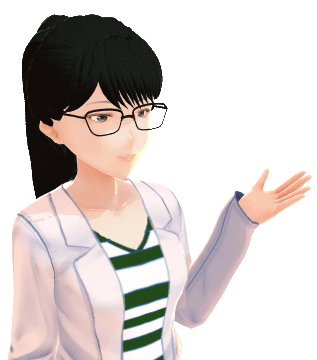
思考の異常パターンにはいろいろあります。
『思考奔逸』は、考えが次々の方向性も定まらずよどみなく浮かんでくる状態です。
思考過程の統制が低下しているので、連想から次の連想までの時間が短く、注意がそれやすい状態です。
連想は、一応関連性は保たれているものの、全体としてまとまりがなく、ちょっとした刺激で注意がそれてしまいます。
考えが目的をもって秩序立てることができず、ひどくなってくると言っていることが支離滅裂になってきてしまいます。
『思考抑止』は、連想から次の連想に時間がかかるので、会話が先に進まない状態です。
連想的着想が少なく、言葉数も少なくなり、持続的に思考の流れが緩慢になってきます。
『思考途絶』は、思考の流れや過程が突如として遮断されます。
『迂遠』は、思考のスピードは正常であるものの、思考の過程が回りくどく、細かなことや関係がないことにこだわってりするため、結論や目標に達するまでに時間がかかります。
『保続』は、同じ観念が繰り返し現れ、思考が1カ所に停滞するため、考えの方向を変更することできずに同じことを繰り返して話したりします。
妄想とは
精神疾患による妄想(delusions)は、事故に結びついた誤った確信になります。
よく、所属している団体の文化である迷信であったり、いろいろと架空の事柄を空想したりすることも妄想といったりしますが、病的な妄想とは区別されます。
妄想は、通常の信念とは比較にならない強い確信で、そのためどんなに論理的反証をあげたとしても、訂正することができないようになっています。
妄想の内容は不合理で、ほとんどが自己に関係したことになっています。







