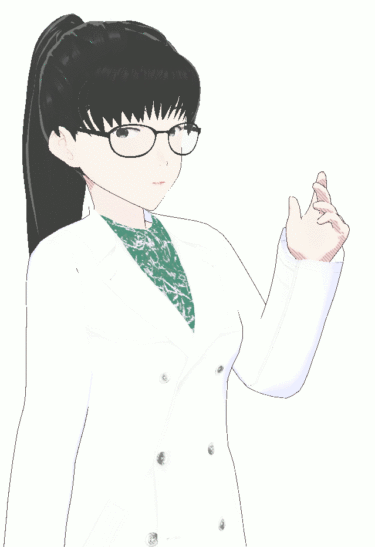漢方における治療の原則には、扶正祛邪(ふせいきょじゃ)、治病求本(ちびょうきゅうほん)、随機制宜(ずいきせいぎ)などがあります。
扶正?邪
『扶正祛邪(ふせいきょじゃ)』は、正気と病邪のバランスを見て、診断治療していくというものです。
漢方では、全ての病気は、病邪(邪気)が正気の力を上回ったときに発生するとされています。
邪気とは体を攻撃するもので、正気は人体に正常に存在している気・血・津液で、現代の西洋医学風に言えば免疫力になるのかもしれません。
漢方の治療においては、正気を助けて邪気を攻撃するというのが大原則になっていて、正気を補う補法、邪気を排除する瀉法によって治療していくという考え方になっています。
虚証の場合は正気を補う補法、実証の場合は邪気を排除する瀉法ということで、『扶正?邪』は『補虚瀉実(ほきょしゃじつ)』と言われたりもします。
だたし、?邪を行うと正気も消耗してしまうので、長期の治療となる場合には、正気を補いながら邪気を攻撃していく攻補兼施(こうほけんし)が行われたりします。
治病求本
『治病求本(ちびょうきゅうほん)』は、病因の本質を見極めることから始めるということになります。
漢方では病気の本質的な事柄を『本(ほん)』、そうでないもの、現れている症状を『標(ひょう)』と言います。
漢方においては、まずは表に現れている症状を対症療法的に片付けてから、根本原因である本に進んでいく『先標後本』が治療の基本になっています。
本は裏にあって慢性化する場合が多いので、先表後裏とか、先急後緩などと言われたりもします。
しかし、一般的には標と本を並行して治療していく『標本同治(ひょうほんどうち)』で治療が行われることも多いのですが、原則をいうと『治病求本』ということになります。

随機制宜
『随機制宜(ずいきせいぎ)』とは、同じ疾患であっても、気候や地域、患者によって病態が異なり、同じ患者であったとしても環境が変わるとまた変化してくるため、これを考慮して臨機応変に漢方治療を行っていく必要があるという原則です。
随機制宜は、『三因制宜』とも言われます。
『三因制宜』とは、因時制宜(いんじせいぎ)・因人制宜(いんじんせいぎ)・因地制宜(いんちせいぎ)になります。
『因時制宜』とは、四季の気候変化は人の生理機能や病理的変化に対して影響を及ぼしますが、こうした時の流れ、自然に順応した考慮が必要であることを言います。
『因人制宜』とは、人に応じて適時処理を検討することで、患者の年齢や性別、体質、生活環境、社会環境、心理状態などを十分に考慮して治療が行われることを言います。
『因地制宜』とは、地に応じて適宜処理するという意味で、地域の気候条件や生活環境なども考慮して治療が行われることを言います。