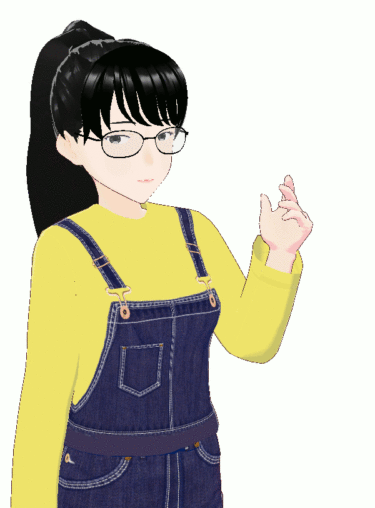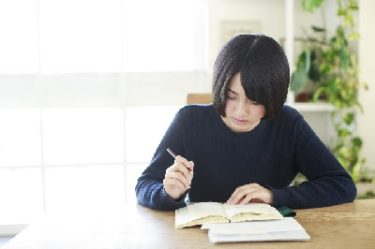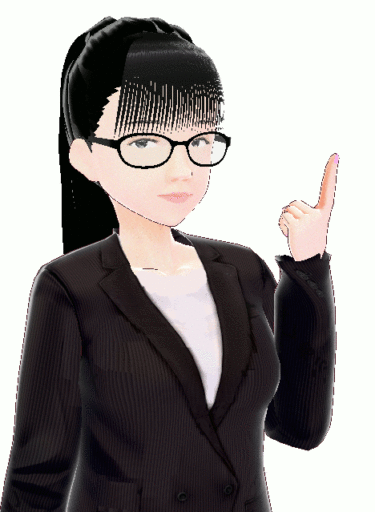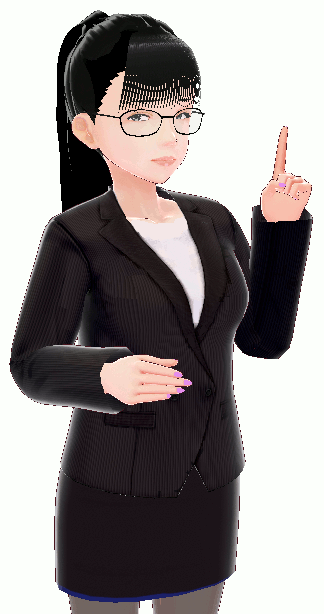ものを見るときに使う器官はという問いに関して、『目』という解答は間違いではありませんが、ものを見るということは、目だけの作業ではありません。
ものを見るための脳
確かに、ものを見た時、その像は目の網膜上に投影されていますが、それは電気信号に変換され、視神経を通って脳の大脳皮質の視覚を担当している視覚野へと伝えられます。
そこではじめて、脳が映像化して、『ものが見えた』となるわけです。
脳でものを見ている証拠

ものを見るのは目という意識が強いと、脳でもものを見てるといわれてもどうもピンとこないという人もいると思います。
たとえば、こんなことはないでしょうか。
夕方疲れてくると、字を読み間違えてしまった。
探し物をしていて、そこにあるはずのものが、なかなか見つからず、あれ?さっきここ探したはずなのに、こんなところにあったという経験がある。
外をボーっと歩いていたとき、顔見知りの知り合いにあったけれど気づかなかった。
実は、このとき目にはその像は映っていたはずなのですが、脳が見ていなかったため気づかなかったのです。
つまり、目の機能がしっかりいていても、脳が見えると判断しないと気づかなかったりするのです。
視力検査のときも、どうせ自分は視力が悪いんだから、どうせ見えないとネガティブな考えを持っていると、それが脳に影響を与え、さらに見えなくなってしまうとケースがあります。
これとは逆に、いやいや見えると思うと集中をしていると、次第に視力検査表のCの輪っか、つまりランドルト環がはっきり見えるようになってきたりすることもあります。
ストレスで目は悪くなる
緊張していると、ものの見え方が悪くなったりすることがあります。
緊張しているときは、自律神経のバランス、つまり交感神経と副交感神経のバランスがくずれて、交感神経優位になっています。
目の黒目の中には、瞳(瞳孔)があり、目はそこで目に入ってくる光の量を調整しているのですが、緊張して交感神経優位な状態になると、瞳孔の周りにある虹彩が縮んで大きくなります。
この状態がストレスや緊張により長く続くと、焦点の深さが浅くなってしまい、ピント合わせに余計な力が必要となり、そのため目のピント調節を行っている毛様体筋が疲労して、視力が低下してしまうのです。
またストレスで自律神経のバランスがくずれると、血流障害が起こり、そのため目に必要な栄養や酸素が十分に行きわたらくなり、目が酸素不足の状態になります。
そうなると、毛様体筋ももちろん、目の機能が十分に発揮できなくなり、視力低下につながってしまうのです。