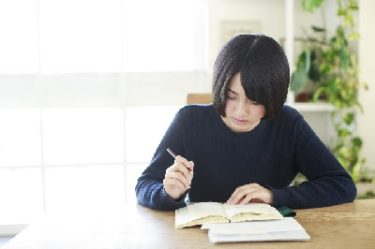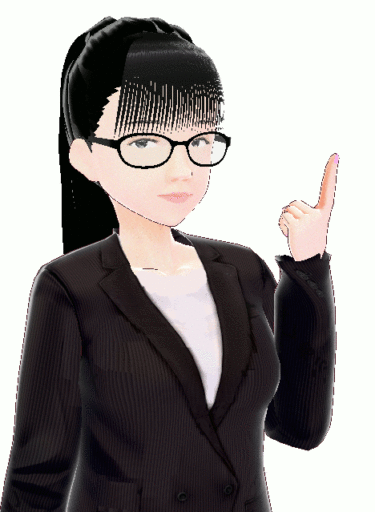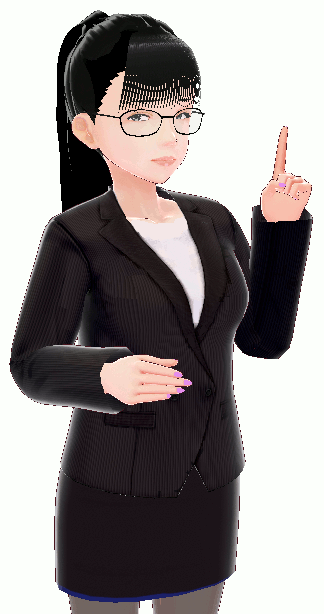人生は時間が限られたものです。1時間は60分で、1日は24時間です。
本をいろいろ読みたいと思っても、1日の時間は限られていて、さらに仕事や学校、家事などで読書に使える時間は限られています。
速読法を身につけたとしても、読める本には限界があります。
できれば、自分にとって役に立つ本を読みたいものです。
できれば効率的に本を読みたい
本を効率的に読むということは、自分にとって役に立つ本をいかに上手に選び、それを読んでいくかになります。
なるべく、自分にとって役に立たない本は読まないことが効率よく本を読むことにつながります。
もっとも、読書好きが読む文学書であるとか、漫画や趣味の分野の読書は、読むこと自体が楽しいのでそれはそれで問題ないのですが、仕事関係やその周辺知識に関する本や、自己啓発のために読むビジネス書などは、効率的に読んでいきたいものです。
本を読む前の事前リーディングとは
事前リーディングとは、『本を読む前に本を読む』ということになります。
サンドイッチマンの富沢さんが聞いたら、「何言ってるんだかわからない・・・」となりそうですが、要は本格的にその本を読む前に軽く目を通すということが、事前リーディングになります。
どんなことをするのかというと、平たく言えば「ざっと見渡す」ということで、スキャニングをするということです。
その本は読むに値するかどうかというスキャニングにもなります。
チェックする項目としては、この本は何について書かれていて、どんな構成になっているかをおおまかに把握することです。
本をチェックするポイント
本をチェックするポイントとしては、まずは本のタイトルやサブタイトルです。
本の購入は、タイトルやサブタイトルで決まるといっていいくらい大切なものです。
自分のお気に入りの著者が書いているというのでなければ、私たちがその本を読むかどうか、あるいは興味をひくかどうかについては、第一段階として本のタイトルで判断している部分はかなりあると思います。
次に本の表紙や裏表紙に書かれた文章、あるいは前書きやあとがき、序章などに軽く目を通すと良いでしょう。
ここにその本のエッセンスなるものや、何を伝えようとしているのかが書かれていたりします。
そしてその次に見るのが、目次や索引です。
目次はサイトマップのようなもので、この本にはどんなことがどんな構成で書かれているのかが一目瞭然でわかりますし、索引を見れば、この本はどのような知識について書いてあるのかがだいたい見えてきます。
雑誌記事やレポ―トの効率良い読み方
まずはタイトルや見出し、そして小見出しを読み構成をつかみます。
次に太字になっているところ、アンダーラインになっているところ、傍点部分などを拾い読みしていきます。
そして最後の段落を読むと良いでしょう。
論文などは、最初のサマリーを読み、いきなり結論を読み、図表をパラパラっと見て、精読するかどうか判断する人もいます。
結論を読んで、興味があれば、論文の内容を精読していくのです。
本の中でも読む部分と読まない部分
本の中でも、例えばこの本の3章と5章は自分に役立ちそうだけど、他の部分はそうでもなさそうだというのであれば、3章と5章だけを読めばいいですし、その中でも読んでいてこのパラグラフは自分にとってそれほど役に立ちそうもないなとか、すでに知っていることだよという場合は、さっと読み飛ばしてしまうのが効率の良い本の読み方です。
本でも100%自分の役に立つという本はそうそうないでしょうし、また逆にある目標をもって選んできている本ならば、全く役に立たない部分ばかりということもないと思います。
同じ本のなかでも、流すところと、じっくりと精読するところを分けた方がよいでしょう。
事前リーディングにかける時間は
本の選択のために使う時間ですので、そんなに時間をかける必要もありません。
ビジネス書や自己啓発書であれば、前書きやあとがきを斜め読みして、目次にざっと目を通して、パラパラとめくり、興味ある図表や写真があるかをチェックする程度で良いでしょう。
もし読みたいと思う本がたくさんあったり、多くの本の中から選択に迷っているのであれば、だいたい1冊1分~2分を目安に事前リーディングしてみると良いでしょう。
それにより、読む本・読まない本を選定したり、読む本の優先順位をつけたり、この本をメインにこの本はサブに、この本はわからないところを調べるためにというように本の役割を決めていっても良いでしょう。
なお、この方法はビジネス書やちょっと興味をもった分野の本を読むときにオススメです。
自分の仕事に関する専門分野の本や、本格的な趣味に関するは、もう少しじっくりと考えていっても良いでしょう。