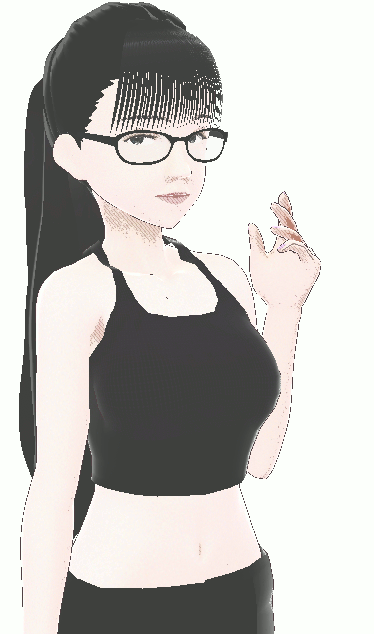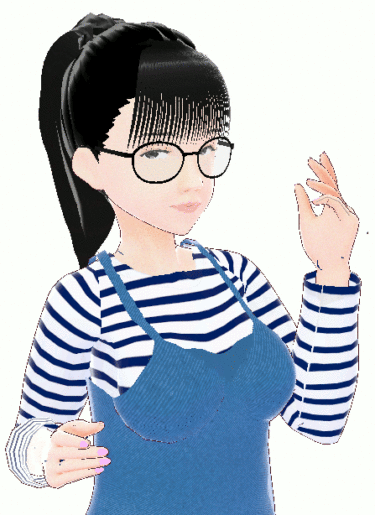人間の肌は敏感で、季節の変わり目や体調の変化などでも日々変わっています。
生理の前後であったり、妊娠であったりしても、肌は常に微妙な変化を受けているものです。
従って、いつも使っている化粧品であったとしても、合わなくなったりすることもあります。
化粧品の成分記載の流れ
今でこそ、化粧品は配合成分を全て記載する全成分表示が原則になっていますが、全成分表示が義務付けられたのは21世紀に入ってからのことです。
2001年4月に、薬事法(現在は名称が変わり医薬品医療機器等法になっている)の表示制度が改訂されて、化粧品は一品ごとに全成分表示をすることが義務づけられるようになり、さらにその全成分表示は、一定の配合量以上の成分については、配合量の多い順に記載しなければいけなくなっています。
従って、製品のパッケージや容器の全成分表示をみれば、どの製品にどのような成分が入っていて、その配合量は多いのか少ないのかというのがだいたい見当つくようになっています。
ところが、現在の全成分表示になる前は、特定の指定成分のみが表示されていました。
化粧品の旧表示成分

化粧品の旧表示成分は、1980年に薬事法により定められています。
化粧品の安全性のため、ごくまれにアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性がある成分として、表示が義務付けられた特定の成分が化粧品の『旧表示成分』で、香料を含めて103種類の成分が指定されていました。
この『旧表示成分』の記載により、アレルギー症状を起こす人や敏感肌の人が化粧品を選ぶ時の一応の目安になっていたのですが、これらの成分が入っていなければ安全な化粧品であるという誤解も生じてきました。
またアレルギーの原因成分は個人個人違うことから、特定の成分だけに注意喚起を促すのは適切ではないとして、配合されている全成分を表示して、消費者が一人一人、自分に合わない成分をチェックできるようにと全成分表示へと移行することになったのです。
化粧品で異常を感じたら
はじめて使う化粧品はもちろん、今まで使っていた化粧品でも、体調などにより肌に異常を感じることもあります。
化粧品を使用して、万一、肌に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常があらわれた場合は、すぐに使用を中止し、症状の改善がない場合は、できるだけ早く皮膚科などを受診するようにしましょう。
受診のときは、使用していた化粧品をすべて持参すると良いでしょう。
肌に異常を感じたら、まずは使用した化粧品を洗い流します。
そして患部を水で冷やします。
必要以上に手で触ったり、タオルでこすったりせず、紫外線も避けるようにし、アルコールや刺激物はとらないようにします。