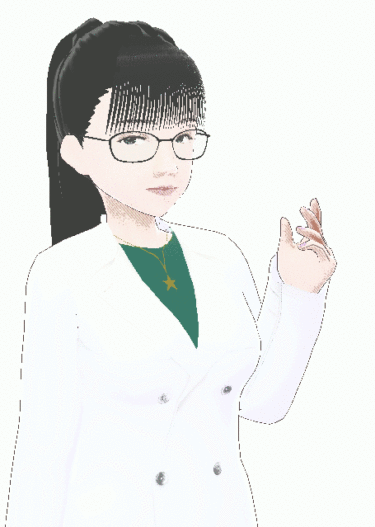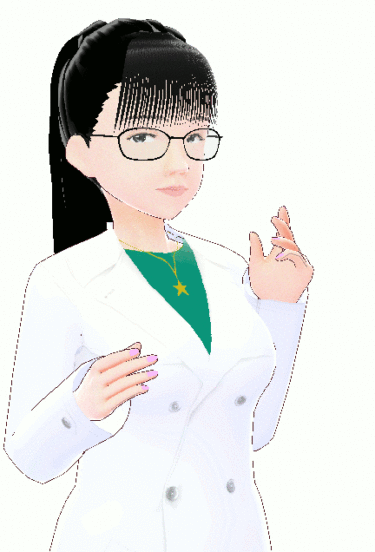身体計測は、肥満度の判定や、メタボリックシンドロームの診断に役立てられます。
体重の測定
体重(Body Weight)は、家にある体重計などで毎日測定している人もいると思います。
基本的には、体重計の測定台にノリ、その中央に静止して軽量します。
衣服を着たまま測定する場合もありますが、コートや重量のあるものははずして測定するようにします。
衣服を着たまま測定する場合は、あらかじめ衣服のおおよその重量を測定された体重から差し引くという方法が取られています。
体重計は、通常は0.1kg単位以下まで測定できるようになっています。
身長の測定
身長(Body Stature)は、靴を脱ぎ、靴下も脱いで両かかとをたがいにつけて、背中・臀部・かかとを身長計の柱に接するようにして直立した状態で測定します。
測定時は、両腕は体の横に垂れ、頭はややあごを引いた状態で測定します。
高齢者で背中が丸くなっている人の身長はどう測定するんだという疑問があると思いますが、そうした場合は測定しない場合もあります。
身長については、成長期でなければあまり変化が少ないために、2~3年に1回の測定でも問題ないでしょう。
腹囲の測定
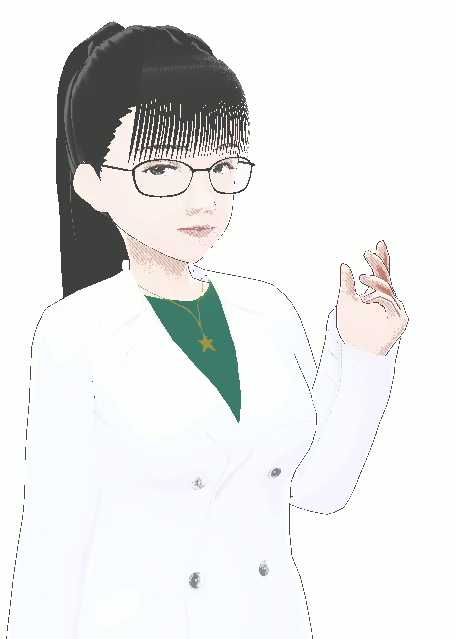
腹囲(Waist measurement)は、メタボリックシンドロームの診断に用いられる測定項目になりますが、意外と測定法が間違っていて、実際とは異なった場所を測定していたりすることがあるので注意が必要です。
腹囲は、力を抜いて立った時のへその高さで計測します。
測定時には、両足をそろえ、両腕はからだの横に自然に下げ、おなかに力が入らないようにします。
巻き尺を腹部に直接当て、その巻き尺が水兵にきちんと巻かれている状態で、ふつうの呼吸をしてもらい、息を吐いた終わりに0.5cm単位まで読み取ります。
腹囲を測定するときに、気になって腹部をのぞきこんでしまう人がいますが、そうすると測定値がずれてしまいますので注意が必要です。
また、腹囲を測定する場合は、できるだけ飲食してから2時間以上経過してからのほうが良いでしょう。
もし一人で腹囲を測定する場合は、鏡の前に横向きに立ち、巻き尺が水兵に巻かれていることを確認して行うと良いでしょう。
日本人の腹囲の基準値は、男性85cm、女性90cmとなっていて、腹囲がそれ以上の値で、加えて脂質・血圧・血糖値のうち2項目以上が基準を超えると、メタボリックシンドロームと判定されます。
BMIとは
BMIは、Body Mass Index :ボディーマス指数のことで、次の式で算出されます。
BMI=体重(kg)÷身長(m)の二乗
身長に対して、BMIが22である体重が、標準体重(理想体重)とされているので、標準体重は次の式で表せます。
標準体重(kg)=身長(m)の二乗×22
日本肥満学会の基準によると、BMIが18.5未満は低体重、18.5~25.0未満は普通体重で、25.0~30.0未満は肥満(1度)、30.0~35.0未満は肥満(2度)、35.0~40.0未満は肥満(3度)、40.0以上は肥満(4度)で、肥満(3度)以上を高度肥満と定義しています。