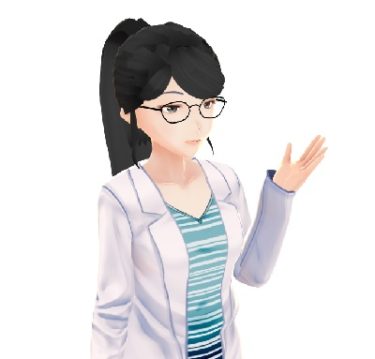天然痘の予防というと、種痘というイメージで、西洋医学のほうがはるかに進んでいるように感じますが、実際のところはどうなのでしょうか。
消毒で進んでいた東洋医学
消毒というと、西洋では12世紀のイタリアで、初めて水銀軟膏が消毒剤として使用されています。
しかし中国では、それより1000年以上昔から、お酒が外傷の傷口からの感染を防ぐ目的で使われていました。
中国最古の医学書と言われる『五十二病方(ごじゅうにびょうほう)』では、感染症である疥癬に、二酸化ヒ素や水銀などの消毒剤を使うことが記されています。
解剖学も古くから発展していた東洋医学
解剖学というと、西洋医学の得意とする分野というイメージがあります。
西洋の最も古い解剖学はアレキサンドリアのヘロヒロスの解剖学があり、紀元前300年ぐらいの時代になります。
実際のところ、人体の解剖が大学で行われたのは12世紀になっています。
中国の解剖学といえば、黄帝内経(霊枢)経水篇に、「解剖して之を見るべし」という記載があり、古代中国においても解剖が行われていたことがうかがうことができます。
11世紀には『欧希範五臓図(おうきはんごぞうず)』、12世紀には『存真環中図(そんしんかんちゅうず)』という解剖書が書かれています。
東洋医学もけして西洋医学に遅れ劣ることなく、独自の発展をとげてきていることがわかります。
天然痘の予防と東西医学
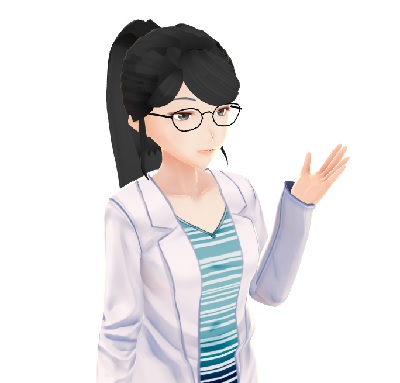
天然痘の予防となれば、エドワード・ジェンナーが、牛痘接種によって、天然痘予防の方法が発表されているのは有名な話です。
ジェンナーは、弱い天然痘である牛痘にかかった人は、牛痘患者にできた水疱の液体を接種すると、天然痘にかからないということを発見しました。
中国でも天然痘に対しては、明の時代に治癒期の天然痘患者のかさぶたを粉末にして、鼻腔内に吹き付ける『早苗法』というような方法が行われていました。
また患者のかさぶたの水溶液を鼻腔内に少量塗る『水苗法』という方法も行われていました。
こうした予防法が17~18世紀の書物である『張氏医通(ちょうしいつう)』や『医宗金鑑(いそうきんかん)』などに記載されています。
日本では、江戸時代、天然痘の予防法として西洋医学が伝わり、やがて日本では西洋医学が東洋医学に代わって広まっていくようになりましたが、天然痘の予防法ということにおいては、中国のほうが西洋よりも先だったといえるでしょう。
西洋医学と東洋医学を比較すると、東洋医学は古い歴史はあるものの、感染予防ということに関しては、西洋医学のほうがずっと進んでいるというイメージを持ってしまいがちです。
しかし中には、東洋医学のほうがより早く、その予防法や治療法が確立されていたりもするのです。