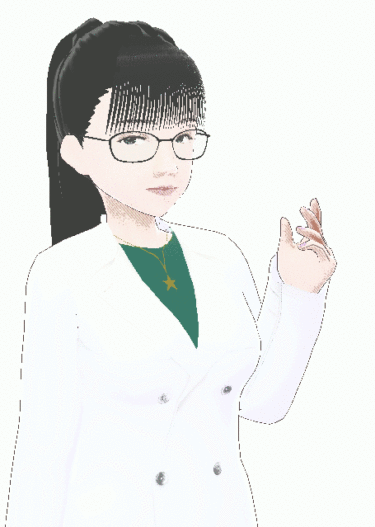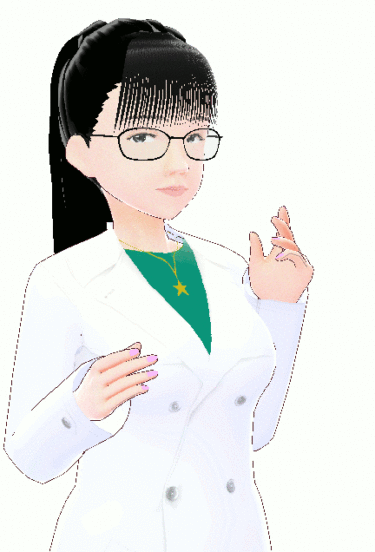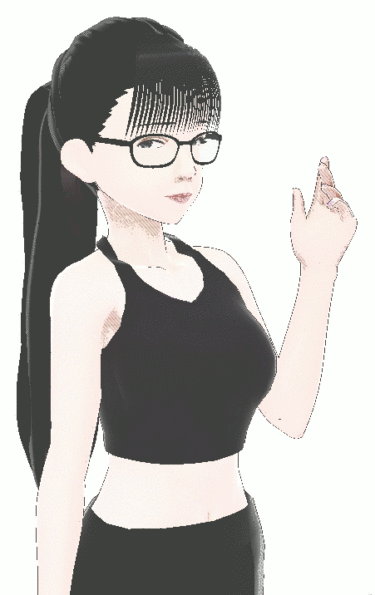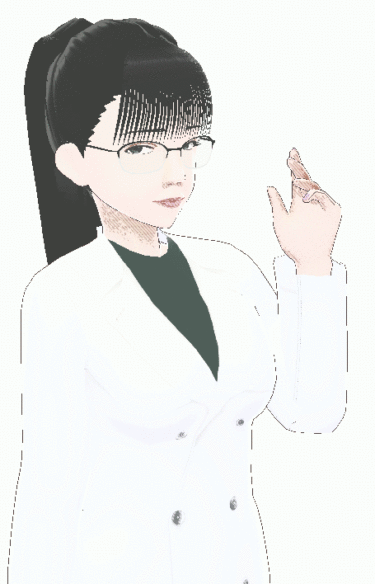日本の教育は、自由な発想を潰す教育をしてきました。
非常に弊害がある教育法です。
言い方を変えれば、常識にこだわりすぎ、好まれる回答でなければ、理由も聞かず不正解として、個性を奪ってきた詰め込み主義の教育が行われてきたといっても過言ではないと思います。
「〇肉〇食」の答えは
例えば、漢字の書き取り試験で次のような問題が出たとします。
【問題】次の〇に漢字を入れて、四字熟語を作りなさい
当然、出題者側が狙っている答えとしては、『弱肉強食』だと思います。
しかし、この問題に対して「焼肉定食」や「拒肉菜食」や「牛肉断食」などと書いたら、不正解にしてしまう教師がいます。
不正解にするどころか、「おまえ、ふざけているのか!」となるわけです。
これは、考えることよりも、覚えること、知識偏重教育をしてきた日本教育の非常に大きな弊害です。
子供の自由な発想の芽を摘んでしまっているのです。
本来であれば、「焼肉定食」や「拒肉菜食」などと発想した子供は、褒められ賞賛されるべきです。
出題側が、自分たちの意図に反する答えをしたものは、反逆児と言わんばかりに怒るなどとは言語道断です。
そもそも「〇肉〇食」の答えはいくつもあるという発想に立てない教師側に問題があります。
一問一答主義にとらわれすぎると、自由な発想の芽を摘んでしまうのです。
考え方はいろいろ

もう一つ、問題を出しましょう。
【問題】A=25 a=5とします。それではB=16の時、bの値はどれでしょうか。
イ:4
ロ:6
ハ:3.2
ニ:14
多くの人は、イ:4と答えたと思います。
25=5×5 16=4×4 だから、答えはb=4
もちろん正解です。
しかし、小文字は大文字の第一桁目の数とすれば、b=6になります。
小文字と大文字の合計が30と考えれば、b=14になります。
小文字は大文字÷5と考えれば、B=3.2になります。
この問題文からは、どれも正解ということになります。
自由な発想は多くの引き出しをつくる
もちろん、何でもかんでもひねくれた回答をすればいいということを推奨しているわけではありません。
ただ、一つのものごとをいろいろな方向からとらえ、多面的にとらえる訓練、思考を深く掘り下げる訓練は大切です。
ある目的を達成するために、その方法が1つしかないのと、いくつもの引き出しを持っているのでは違ってきます。
引き出しを多くもっている人は、ある方法でトラブルが発生しても、それじゃ、こっちの方法でやってみようかということで、目的を達成することができます。
多くの引き出し、発想をもつということは、いろいろなことを考え実行していくにあたり有利になりますので、時には自由な発想の翼を広げる練習をしてみるのも大切なことなのです。