骨粗鬆症の治療薬のビスホスホネート製剤の副作用に、顎骨壊死や非定型大腿骨骨幹部骨折といったものがあります。
骨粗鬆症の治療薬なのに、副作用に骨折とか骨壊死とかってどういうことなのでしょうか。
骨粗鬆症は骨密度だけではない
骨粗鬆症というと、「骨密度が足らない」という話を聞いたりするためか、骨粗鬆症というと骨密度という連想をする人は多いと思います。
確かに『骨密度』は、機器によって簡単に測定でき、骨密度の測定ができる機器も販売されていたりします。
また、整形外科などに行くと、よく骨密度を測定されたりします。
しかし『骨密度』は、骨粗鬆症の直接的な指標というよりは、骨量を表す指標になります。
しかし、骨粗鬆症とは、骨強度(骨の強さ)が低下することにより、骨折しやすい状態になっているものを言います。
つまり骨粗鬆症に関係が非常に深いものは『骨強度』ということになります。
そしてこの『骨強度』は、骨量の指標となる「骨密度」と骨の構造など「骨質」の2つの要因によって決まります。
骨粗鬆症のリスク
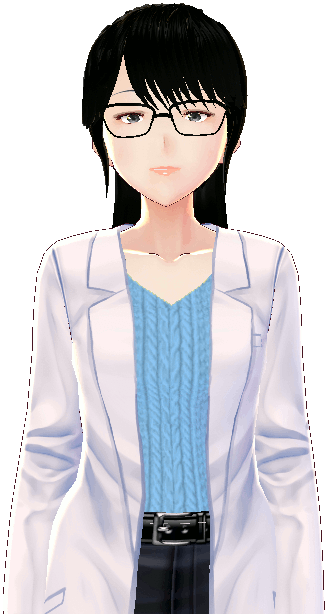
骨密度で測定できる骨量は、成長期に増加して20歳頃に最大骨量に達します。
それ以降はしばらく比較的安定に推移するものの、加齢に伴い減少していきます。
特に女性では、閉経に伴って骨量が減少しやすくなってしまいます。
骨粗鬆症のリスクとして、加齢であるとか、女性であるとか、家族歴といったものは、どうすることもできませんが、普段の生活習慣によって骨粗鬆症のリスクを軽減することができます。
十分なカルシウム、ビタミンD、ビタミンKの摂取、食塩やリンを過剰摂取しない、運動、日にあたるといったことで、骨粗鬆症のリスクを軽減できるのです。
骨粗鬆症のリスクは、骨の強さと関係しますが、カルシウムをきちんと摂取することで、新しい骨が作られる一方、古くなった骨は壊され、カルシウムが骨から溶け出して、骨が新しく置き換わることによって骨の強さが保たれていきます。
骨粗鬆症の治療薬、ビスホスホネート製剤の注意点
骨粗鬆症の治療薬の選択肢の1つとして、ビスホスホネート製剤があります。
ビスホスホネート製剤は、破骨細胞の動きを止めて、アポトーシス(細胞死)を誘発する働きがあります。
すると、骨芽細胞で作られた新しい骨により骨密度は上がります。
しかし、破骨細胞の働きが抑えられてしまっているため、古い骨が回収されないもままとなり、骨としてはもろくなってしまう可能性があります。
建築に喩えると、古いビルを壊さず、その残骸も片付けない状態で、新しいビルを建てているようなものなので強度が落ちてしまう可能性があります。
ビスホスホネート製剤の添付文書をみると、副作用に、非常にまれなものの重篤な副作用として顎骨壊死や非定型大腿骨骨幹部骨折(atypical femoral fracture:AFF)などがあります。
従って、歯を抜くといったような歯科治療を受けている人は、歯科医にビスホスホネート製剤を飲んでいる旨を伝えることが大切なのです。
骨粗鬆症の薬を飲んでいて骨密度上げてるはずなのに、なんで副作用に骨折なんて言葉があるのと思うかもしれませんが、こういったメカニズムがあるのです。
服用にいろいろ注意があるビスホスホネート製剤
ビスホスホネート製剤は、服用するさいに細かな制約があるので注意が必要です。
「朝起きてすぐ、コップ一杯 (200mLくらい) の水道水 (ミネラルウォーターは不可) で飲む。その後30分以上は横にならない」
朝起きてすぐ飲むのは、他の食べ物や薬と混ざると吸収が悪くなってしまうからです。
コップ一杯の水で飲むのは、食道に付着すると潰瘍や炎症を起こす可能性があるからです。
ミネラルウォーターではなく水道水(軟水)で飲むのは、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分により吸収が妨げられるからです。
服用後30分以上は横にならないというのも、食道に付着すると潰瘍や炎症を起こす可能性があるからです。







