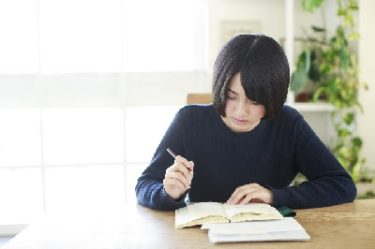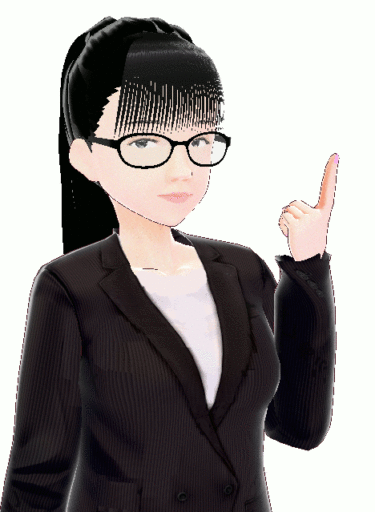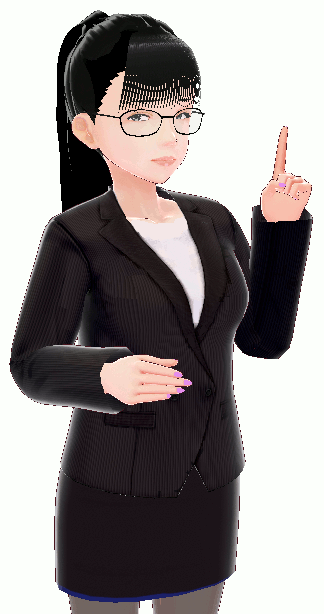好きこそものの上手なれとはよく言ったもので、人間好きなものに関連した知識はどんどん貪欲に吸収できるものです。
記憶力は興味の対象かどうか
記憶力は興味の対象になっているかで大きく変わってきます。
学校の勉強もろくにできず、覚えられないという人が、ポケモンの名前や特徴を事細かに覚えていたりするものです。
つまり、記憶力が悪くて勉強ができないのではなく、興味がなくて覚える気がないということなのです。
仕事でTOEICのテストを受けなければならなくなったとき、英単語を必死に覚え直そうとしても、なかなか頭に入ってこないので自分は記憶力が悪いのではないかと思い込んでいる人もいます。
でもこういう人に競馬の話しをしてみると、馬の名前はもちろん、血統やら性格やらスラスラとでてきたりします。
人間、興味ある事であれば覚えられるものです。
一番危険なのは、知識を得たいという欲求が無くなること
本来、人間は歳を重ねるとともに経験が蓄積され、知識も積み重なっていきます。
それに伴ってより高度な知識や関連分野への知識の欲求というものが強くなっていくものです。
特に、自分の趣味が興味を持って極めているもの、または自発的に勉強を始めたものについては、歳を重ね、知識も豊富になっていて、もっとより知りたいと思うようになるのが普通です。
しかし、この好奇心、知識を得たいという欲求が無くなってきているのであれば、それが一番の問題です。
小さなことからコツコツと興味を沸かせる
歳をとってから、新たな分野のことを勉強・学習しようとしてとき、最初から分厚い専門書を読む人がいます。
もちろん、これで勉強できる人は良いのですが、慣れていない分野の分厚い専門書を最初から読むのはちょっとハードルが高くなります。
無理して読めば、勉強が嫌いになってしまう可能性だてあります。
こうした場合は、薄い入門書などを手始めに読んでみると良いでしょう。
その中で疑問に思ったことをネットなどで調べているうちに、好奇心が刺激されて、もっと知りたいというようになっていくものです。
こうなればしめたものです。
調べる習慣が大切
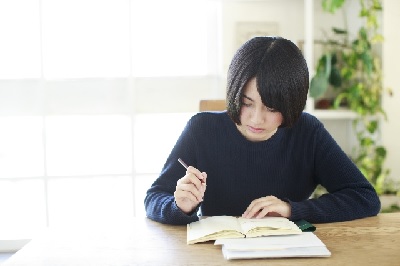
会話をしていても、本を読んでいても、わからない言葉が出てきたり、わからないことがあるとすぐにネットや本で調べる人がいます。
思い出せなかった言葉yあ、知らない言葉をそのままにしておくのが気持ち悪いのです。
今では、わからないことがあってもすぐにその場でスマホで検索できる便利な時代です。
このわからないことがあったらすぐに調べるという姿勢がとても大切なのです。
こうしてわからないことをすぐ調べる習慣がある人は、どんどん知識量が増えていき、それがさらなる好奇心の高まりにつながります。
勉強や学習で大事なことは、好奇心です。
好奇心がでてくれば、さらにもっと知りたいという欲求が高まり、さらに知識量が増えていくという好循環に入り、勉強は楽しいものというようになっていくからです。