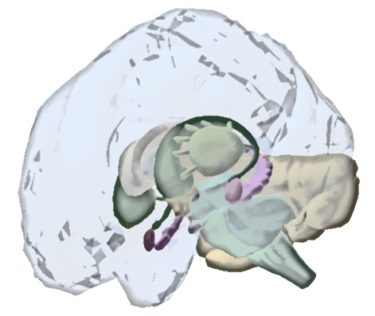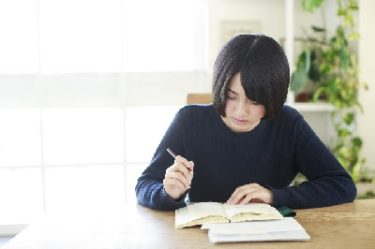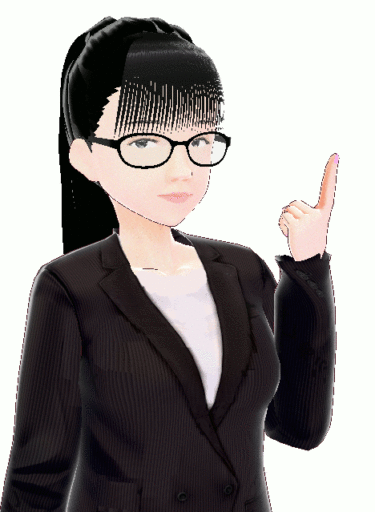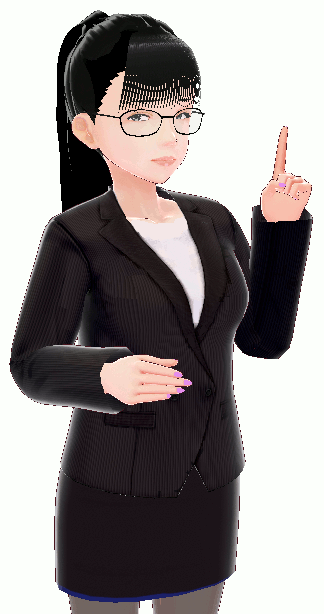私たちが普段触れている情報は、その大半が忘れ去られていると言われています。
実際に、昨日の朝は何を食べたのか、先日行った旅行先の地名など、別に忘れてしまっても生活に支障はありませんし、ましてや人生に大きな影響などないでしょう。
しかし、忘れてはいけない約束事、取引先の人の名前、受験勉強、資格試験といったように、忘れられないものもあります。
忘却の4つのパターン
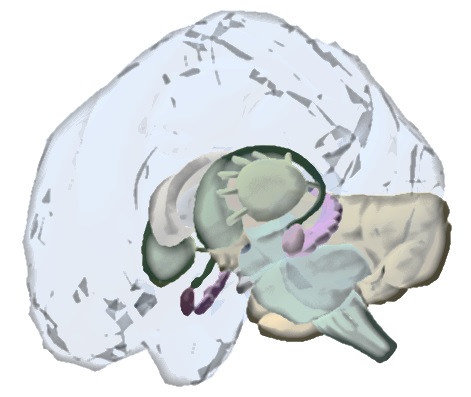
私たちは、なぜ忘れてしまうのかということですが、忘却には4つのパターンがあります。
それは、未記憶、記憶の減衰、記憶の干渉、手がかり依存性忘却です。
未記憶
忘却の4つのパターンの1つ、『未記憶』とは何かといえば、平たくいえば「記憶していない」ということです。
日常生活においての物忘れといわれるものの大半は、この未記憶によるものと言われています。
実際には意識して覚えていないのに、覚えた気になっているのであって、この場合は、しっかりと覚える対象に注意を向けるなどして、しっかり覚えることが大切です。
記憶の減衰
未記憶ではなく、ちゃんと適切に記憶したはずなのに、時間がたつと思いだせなくなっていることがありますが、これが記憶の減衰です。
例えば、試験勉強で、ある知識に関して記憶したとき、しっかりと覚え、数分後にチェックしたときも、1時間後に見直したときも、確実に覚えられたという感覚があったのに、いざ試験のときに思いだせなかったというもどかしさを経験した人も多いかと思いますが、これが記憶の減衰です。
記憶は、スキー場のシュプールと似たようなものです。
記憶したとき、つまり滑った直後は、くっきりとシュプールが残っていますが、その後、雪が降り積もったりすると、だんだん薄くなっていき、しまいには消えてしまいます。
シュプールを残すには、また同じところを滑らないといけません。
記憶しても、最低1日は覚えていられるようなレベルにはしておきたいところです。
翌日チェックして忘れていたら、もう一度覚え直し、翌日チェックして覚えていてもまたその翌日チェックをし、しっかり覚えられていなかったら、そこで覚え直すぐらいにしておいてほうが良いでしょう。
記憶の干渉
記憶の干渉は、別に記憶した情報に妨害されて、肝心の情報が思いだせない場合になります。
これを防ぐためには、覚えることをまとめてみたり、干渉を起こしやすいものを意識して覚えるようにすると良いでしょう。
手がかり依存性忘却
これは、覚えるとき手がかりを頼りにして思いだしている場合です。
この場合、手がかりとなるようなものが出てこないと、思いだすことができなくなってしまいます。
思いだす手がかりを多くすることによって、思いだすルートを増やして防ぐことができます。