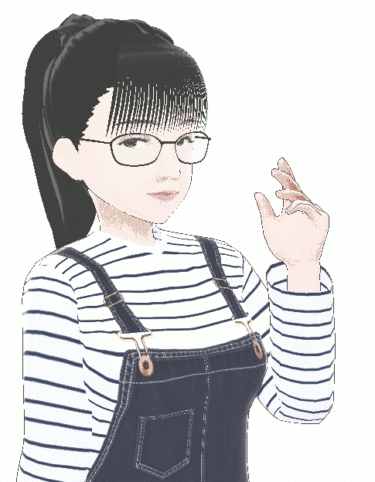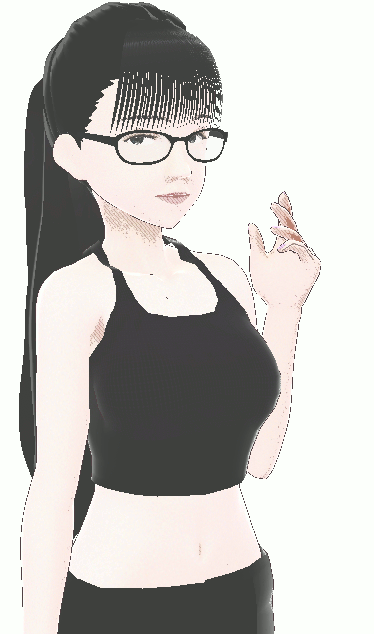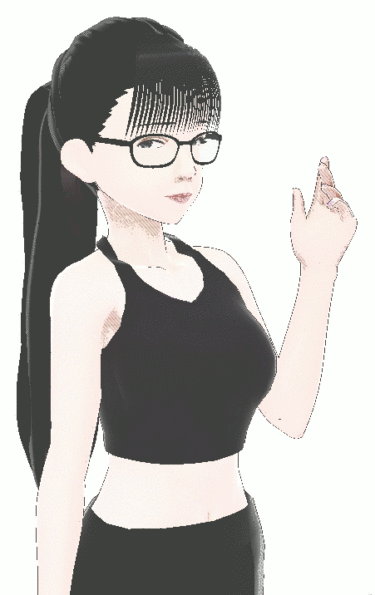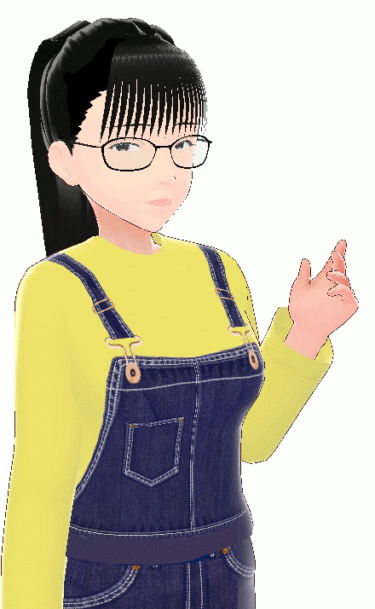カルシウムと血中脂質については、結論を先に言うと関係があるともないともいえないというのが現状です。
学術的にはその関係の説明をつけることができ、臨床においてもカルシウムの摂取により脂肪の吸収が抑えられたというデータもありますが、一方でまったく関係はないという研究結果も出されています。
カルシウムと血中脂質
カルシウムと血中脂質の関係を学術的に考察すると、カルシウムが直接に脂肪の代謝に関わるということはありません。
しかし、脂質が体に吸収される際に重要な働きをする胆汁に対して、カルシウムは胆汁酸や脂質と結合します。
このことによって、カルシウムは脂質が小腸から吸収するのを抑えると考えられます。
実際に、食事中のカルシウム量と吸収されなかった脂肪量の関係を調べた結果、カルシウムは脂肪の吸収を抑えるといった報告も出されています。
それでは、臨床的にどうなのかというと、低脂肪食とカルシウムを組み合わせて、血中のコレステロール値を下げたという研究報告があります。
さらに炭酸カルシウムを低脂肪食ととることによりLDLコレステロールが減り、HDLコレステロールが増加したという研究結果もだされています。
しかし一方で、コレステロールや中性脂肪などの血中脂質濃度には影響を起こさなかったという報告も出ているので、はっきりとしたことは言えないというのが現状です。
カルシウムの栄養機能食品

カルシウムの機能で確かなのは、栄養機能食品として認められているものです。
カルシウムの栄養機能食品は、カルシウムの1日の目安量が、210mg~600mgになっています。
そして「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」という栄養機能表示がされています。
カルシウムの特定保健用食品
カルシウム成分が入っている特定保健用食品は、カルシウムの吸収をよくするため吸収しやすい形にしたものと、虫歯に関連したものと、骨粗鬆症のリスクを低減について言及したものがあります。
いずれにしろ、特定保健用食品は普通の食品と違い、ヒトによる臨床試験等を行い、エビデンスが検証された結果表示が認められた製品になっています。
カルシウムの上手な摂取のしかた
カルシウムは乳・乳製品、魚介類、大豆製品、種実類、藻類などに多く含まれます。
重要なミネラルであるカルシウムは小腸から吸収されますが、その吸収率は、特に乳児期・思春期・妊娠後期で高くなります。
カルシウムは1食で集中的に摂取するというよりも、分けて摂取するほうが効率よく摂取できます。
さらにカルシウムはビタミンDと一緒に摂ることにより小腸上部からの吸収効率が良くなると言われています。
また野菜に含まれるシュウ酸や、玄米等の穀物に含まれるフィチン酸はカルシウムの吸収を抑える働きがあるので注意が必要です。