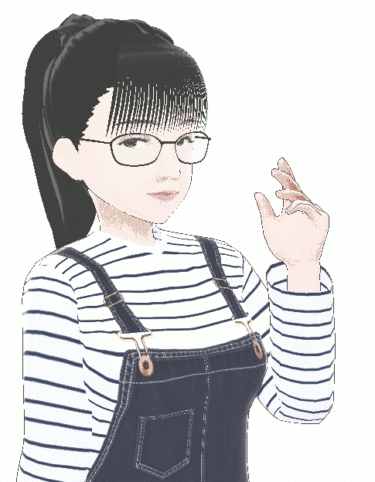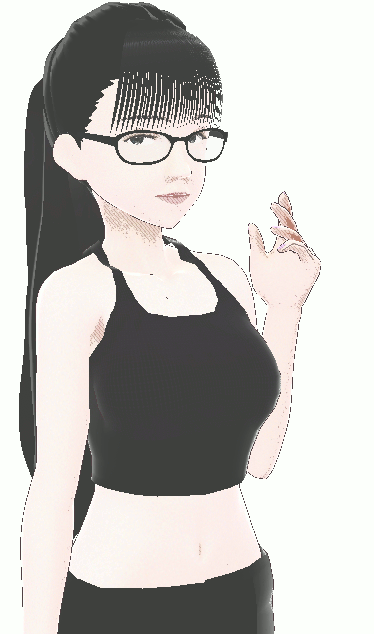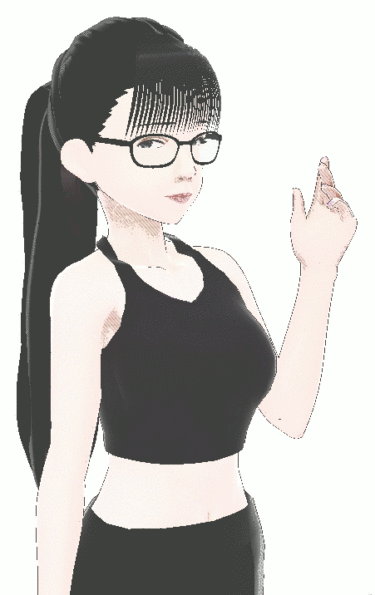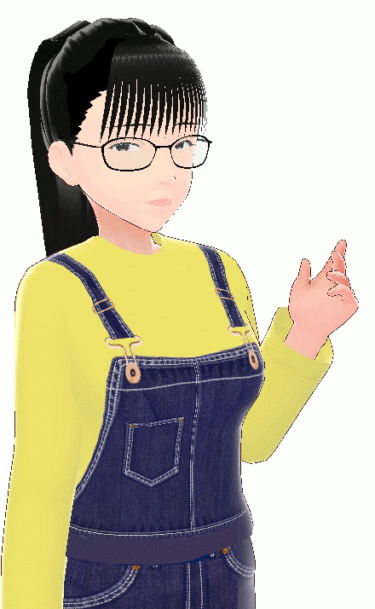優れたリーダーは、教師であると同時に、親代わりでもあると言われます。
教師というのは、いろいろな仕事面や勉強面で学ぶところが多いということになりますが、それと同時に親代わりになるような慈愛の心が大切になってきます。
孫子の兵法に学ぶ
孫子の兵法は、2500年以上も前に書かれたものです。
兵法というと、なんだ戦争の本かと思い、そうであればそんな戦国時代じゃあるまいし、古い古いと一蹴する人もいるかもしれませんが、2500年以上も前に書かれたものなのに、今現在、なお読み継がれているのには、理由があります。
それは、孫子の兵法に書かれていることは、戦争以外にも応用が利くからなのです、
その孫子の兵法に次のような文章が出てきます。
『卒を視ること愛子の如し、故にこれと倶に死すべし』
卒とは兵士のことで、意味としては「司令官が兵士たちをわが子のように思っていれば、兵士たちにもその思いは伝わり、司令官に従って死ぬこともいとわなくなる。」という意味になります。
これを現代風にすると、部下に接する態度は、親がわが子に対するよう慈愛に満ちていなければいめないということを言っています。
そうするからこそ、嫌な仕事、面倒くさい仕事につかせるときでも、リーダーとともに一生懸命やろうという覚悟を持たせることができるということになるのです。
部下を消耗品にように扱う人もいますが、こうしたリーダーはもう論外で失格ということなのです。
慈愛と溺愛は別物
『卒を視ること愛子の如し、故にこれと倶に死すべし』には続きがあります。
『厚くして使うこと能わず、愛して令すること能わず、乱れて治むること能わざれば、譬えば驕子の若く、用うべからざるなり。』
です。
だいたいの意味としては、「ただ兵を手厚く厚遇だけではきちんと使えず、慈愛するだけでは命令もできず、好き勝手やっているのを止めることができないのであれば、たとえばわがままな子供のようなもので、とても使い物にはならない。」となっています。
つまり、慈愛は良いけれど溺愛はよくなく、慈愛と溺愛の違いをはっきりと認識した上で、優しさと厳しさを器用にバランスよく使いこなせる者がリーダーとしてふさわしいと言えます。
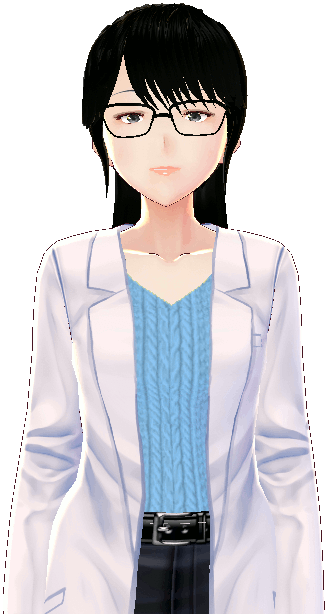
バランスが難しい
部下と接するとき、上辺だけではなく、実際の行動でします必要があり、ただ可愛がればよいわけではありません。
命令通りしっかりと行動してくれるように、厳しくしつけることも大切になってきます。
リーダーは、仕事面では教師のように、技術的にも知識的にも豊富で引き出しが多く、頼れる存在でなければいけません。
そして、心・感情という面を考えた場合に、親代わりのように、ただ甘やかすのではなく、きちんと叱るべきときには叱って、慈愛をもって接しなければいけないのです。
そうすることで、部下からの尊敬や信頼を集めることができ、リーダーとしてふさわしくなっていくのです。