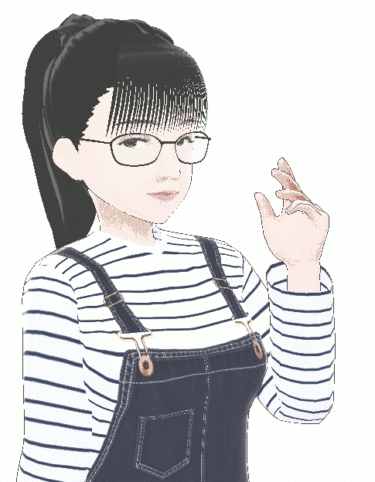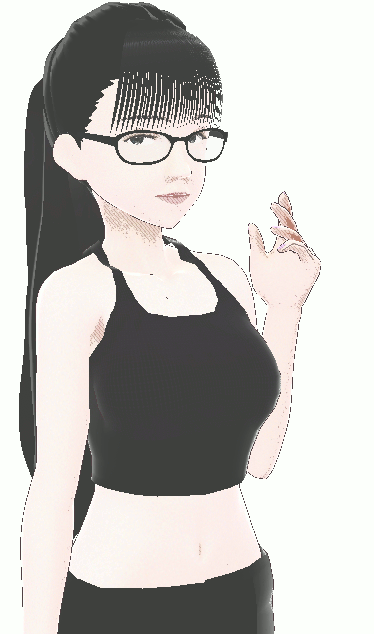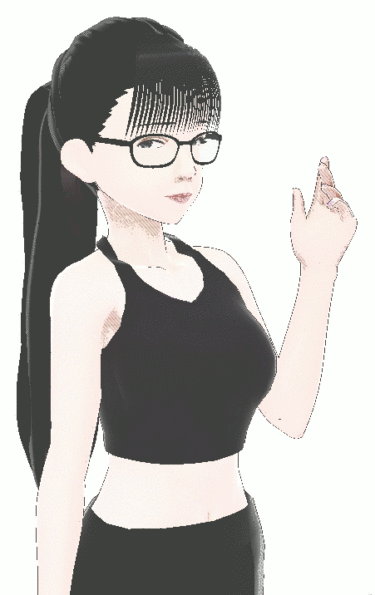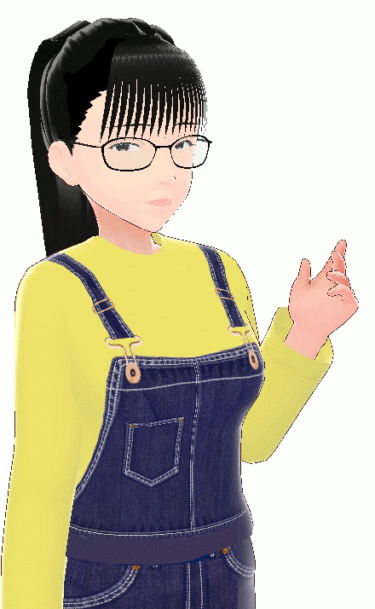ほうれん草などをゆでると、その葉の緑色が溶け出して、お湯が緑色になってきます。
葉っぱを緑色にしている成分は、葉っぱからお湯に溶けだしたこの中にあると推測できます。
クロロフィルが葉っぱの緑色の正体
お湯でも良いのですが、植物の葉っぱをアルコールの中に入れて浸けておくと、葉っぱの緑色がゆっくり溶け出します。
アルコールにずっと浸けておいた葉っぱを取り出すと、アルコールは葉の緑色が完全に溶け出して緑色に染まり、葉っぱは白色になります。
この緑色の正体は、葉緑素、つまりクロロフィルです。
クロロフィルには、色の素になる物質という意味があり、色素になります。
つまり、なぜ葉っぱが緑色なのかというと、葉っぱには緑色色素の葉緑素(クロロフィル)があるからということになります。
葉っぱは夜には緑色に見えない
昼間、白色光の下で緑色に見えていた葉っぱも、夜には緑色に見えません。
葉っぱの緑色は葉緑素(クロロフィル)ということですが、実は、光が当たらない真っ暗な場所では、クロロフィルは緑色ではありません。
もし葉っぱ、クロロフィルが緑色を発光しているのであれば、夜、暗闇の中でも葉っぱは緑色に見えるはずです。

光で緑色になるクロロフィル
白色光は、いろいろな光が含まれていて、虹の7色と表現されたりすることもあります。
しかし、それぞれ7色に境界があるわけではなく、大きくわけると光には、光の3原色というものがあり、それは青色・緑色・赤色です。
この3色が混ぜ合わさることにより白色光になります。
光が葉っぱに当たると、葉っぱに含まれるクロロフィルは、白色光の中で青色光と赤色光を積極的に吸収します。
しかし緑色光はあまり吸収しません。
クロロフィルに吸収されなかった緑色光は反射したり通り抜けたりするため、葉っぱが緑色に見えるのです。
青色光や赤色光はクロロフィルに吸収されてしまい反射しないので、目に入ってこないのです。
下から葉っぱをみても緑色なのは、やはり緑色の光が吸収されずに通り抜けているからです。
それでは、なぜクロロフィルは、青色と赤色の光を吸収するのかというと、それは光合成に効果的だからということです。
葉っぱやクロロフィルにいろいろな波長の光を当てて、その吸収量や二酸化炭素の量を測定することにより光合成速度を測定すると、青色や赤色では光の吸収量が多く、光合成速度も高かったのに対し、緑色では光の吸収量も少なく、光合成速度も低く、光合成の効率が悪いのです。
クロロフィルに吸収される青色光と赤色光によって、光合成が効率よく行われているのです。