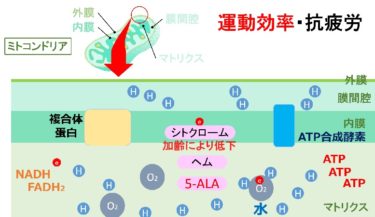『春眠暁を覚えず』という言葉もありますが、ヒトはなぜ眠くなるのでしょうか。それを解き明かすカギとなっているものに『睡眠物質』というものがあるのです。
またヒトの三大欲求といえば、食欲、性欲、そして睡眠欲です。そのぐらい睡眠は大切なのです。
ヒトが眠くなるのはナゼ?
ヒトはなぜ、眠くなるのでしょうか。
「それは、疲れたからだろう」という人もいますが、疲れていてもかえって目が冴えるという場合もあります。
確かに、疲労は眠気を誘う一因とはなりますが、決定的なものではありません。
実は、眠くなることと深く関わっているものに、『睡眠物質』というものが明らかになっています。
眠くなってきたとき、体に何が起きているのか

眠くなってきたとき、いったい体に何が起きているのでしょうか。
実は、眠くなってくると、脳の周りの脳脊髄液にいろいろなホルモン様の物質が分泌されてきます。
それが脳全体に広がることで眠気を誘うのですが、この脳全体に広がって眠気を誘う物質が『睡眠物質』です。
睡眠物質については、1970年代に睡眠に関与している多くの物質が発見されていきます。
動物の脳や血液、尿などから約30種類もの睡眠物質が報告され、研究されています。
眠りを誘うメラトニン
眠りを誘う代表的な成分としてよく知られているのが、ホルモンの一種である『メラトニン』です。
メラトニンは人間の松果体に存在している窒素原子をもったインドールアミンになります。
眠くなってくると、メラトニンをはじめとした睡眠物質は、脳脊髄液の中に分泌されてきます。
神経伝達物質のように、神経のシナプスの間隙を漂うのではなく、脳脊髄液の中に分泌されるのです。
メラトニンは、寝る直前に増加しますが、このことから眠気と深い関係があるのではということでいろいろと研究をされるようになっていきました。
メラトニンは、睡眠を促したり、睡眠リズムを調整する働きがありますが、2010年には、メラトニンの受容体に作用する薬が不眠症治療薬として使われるようになっています。
また、メラトニンとは逆に、脳内のオレキシンは覚醒状態を維持する働きがありますが、このオレキシン受容体をブロックすることで、覚醒状態を抑制して、睡眠状態に導いていくという作用機序の睡眠薬も開発販売されています。
年齢を重ねるとともに睡眠が変わってくる
人間の睡眠は歳とともに変化していきます。
成長期では深い眠りにつきますが、高齢になってくると眠りは途切れがちになり浅くなってきます。
特に高齢の人の不眠では、過去の深い眠りを正常と感じていて、年齢相応の眠りの短さや浅さに不満をもち、それがストレスになり、よけいに不眠になってしまうケースもあります。
高齢になったら、睡眠の質が変わってくるのが普通だと認識することも大切です。