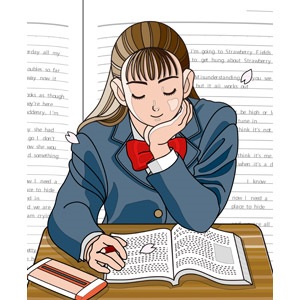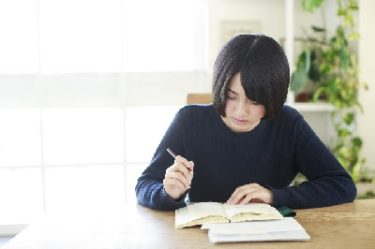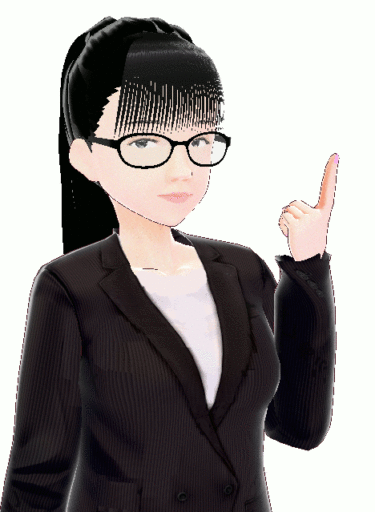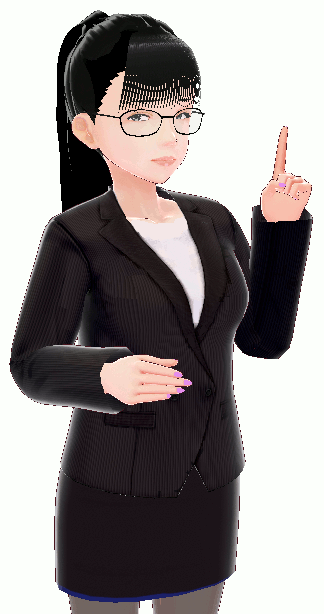英語で、SVOの第三文型で、目的語がto V (不定詞)の形になるのか、Ving と分詞系になるのかで迷うことがあります。
toに注目するとおのずと答えが見えてくる
 SVOの第三文型で to V をとる動詞と、Ving となる動詞をすべて覚えてしまうという方法があります。
SVOの第三文型で to V をとる動詞と、Ving となる動詞をすべて覚えてしまうという方法があります。
確かに記憶力に自信がある人であれば、それも一つの方法だと思いますが、そんなものいちいち全部覚えてられないよという人がほとんどだと思います。
そこでSVOの第三文型で、to V となるのか、Ving がくるのかについては、不定詞部分の to に注目すると理解しやすいと思います。
to は不定詞として使われていて、文法的には副詞ということになりますが、to という単語の意味としては、前置詞の to と同じと考えることができます。
つまり、ひと言で言えば、右向きの矢印。~に向かっていくというニュアンスが含まれます。
目的語で、to V という形にした場合、「これからVする」、「Vする方向に向かう」という意味あいになってきます。
従って、これから行うこと、これからする方向のものについては、to V を使い、そうでない場合は、Ving を使うと考えれば良いのです。
to V と Ving の具体例
decide
 decideは、決定するという意味ですが、決定するというのは、これからのことです。
decideは、決定するという意味ですが、決定するというのは、これからのことです。
もう過ぎてしまったことを決定しても仕方ないわけですし、おかしいですから、dicide は、これからのこと、これから向かおうとしている方向のことについて決定するということになります。
したがって、decide の目的語は、to V (不定詞)となり、Ving は使わないということになります。
つまり、 decide to V という形になるわけです。
promise(約束する)も、約束するのは過ぎたことではなく、これからのことですから、
promise to V となります。
want (望む)も、未来・これからのことについて望むわけですから、
want to V となります。
stop
stopは、他動詞で使われる場合、目的語にくるものは、すでにやっていることということになります。
考えてみればわかりますが、やってもいないことは止めることもできません。
つまり、これからのことではなく、既にやっていることですので、stopの目的語は、to V ではなく、Ving となり、stop Ving となるわけです。
to V 、Ving を目的語にとる場合の例外
英語も言葉ですので、どうしても例外が存在します。
原則は、未来のこと・これからの方向を目的とする場合は、to V の形で、それ以外は Ving と考えていいのですが、例外はあります。
cease to V (Vでなくなる)
cease Ving (Vをやめる)
*後ろの動詞が状態動詞なら to V、動作動詞なら Ving となります。
しない方向に向かうのに、to V を使う例外
hesitate to V (Vすることをためらう)
refuse to V (Vすることを断る)
これからすることなのに、Ving を使う例外
consider Ving (Vしようと思う)
suggest Ving (Vすることを提案する)