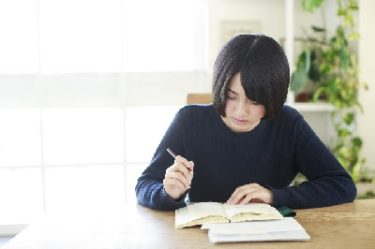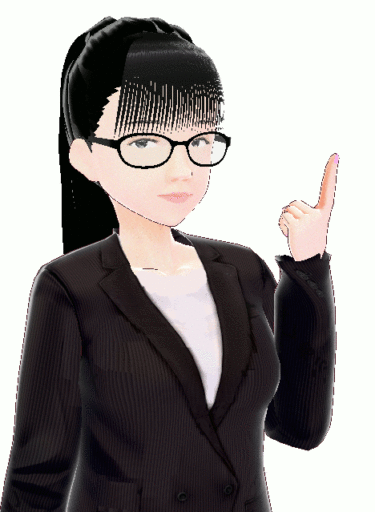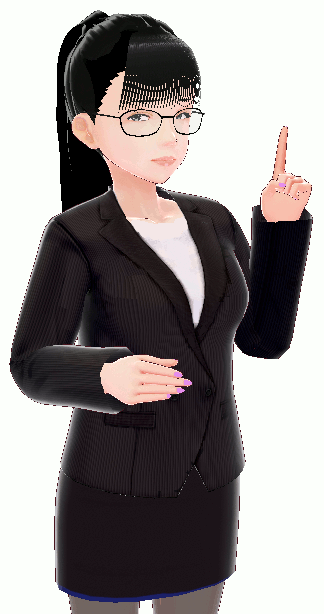人間の脳は、使わないとどんどん衰えていってしまうという人がいます。
脳の容量の限界は
人間の脳は、記憶できる容量が決まっているので、それ以上は憶えられない。
だから私はあまり物事を憶えないようにしているという人がいます。
しかし、事実は全く逆です。
人間の脳は、いろいろなものを記憶して、脳の情報量が多くなっていけばなっていくほど、よりたくさんのことを記憶できるようになっていくのです。
つまり、いろいろな経験を積み、知識を身につけていったほうが、記憶しやすくなっていきます。
なぜ憶えられないのか
人間はものごとを覚えると、それが記憶に入っていきます。
このとき、短期記憶と長期記憶に分かれます。
短期記憶は、数十秒から数十分で頭から消えてしまいます。
一方長期記憶は、数時間から数十年、場合によっては一生涯、頭に保持されます。
もし、短期記憶ができなければ、数字を憶えていられないので暗算はできませんし、推理小説などを読んでいても、名前が出てくるたびにその登場人物がどんな人かわからなくなってしまい、推理どころではなくなってしまいます。
一方、私達が小学生のときならった九九などをずっと憶えているのは、長期記憶になっているからです。
短期記憶と長期記憶

短期記憶は脳の海馬に入りますが、海馬の容量は少ししかありませんので、少し情報を入れるとキャパオーバーになってしまいます。
いわば小さいメモ用紙みたいなものです。
いろいろとやることが重なり、スーパーで買うものを確認して頭にいれていったつもりが、1つ2つ買い忘れてしまうなどというのも、海馬のキャパオーバーによるものです。
長期記憶は側頭葉に入り、こちらは情報が無尽蔵に蓄積されていきます。
よく何年も前に旅行に行ったときの詳細を、あたかも昨日行ってきたように思いだしたり、子供の時の記憶を大人になってもしっかり覚えているのは、この長期記憶にはいっているからです。
憶えているためには、短期記憶ではなく長期記憶に入ればいいのですが、そのためには海馬に入った記憶が、側頭葉の記憶にならなければなりません。
時間が経ってもよく憶えているものにはどんなものがあるのか考えてみると、繰り返して憶えたもの、毎日聞かされたこと、自分の心にはっきりとイメージできたもの、喜びなど感情が強く動いたもの、これは自分にとって大切なものだと強く思っているもの、めずらしくすごく面白いと思ったものなどだと思います。
なぜ、こうした情報が長期記憶として残っているのかというと、繰り返したり、感情が動いたり、ものすごく大切だと思ったりすることで、情報が海馬から扁桃体を経由して前頭連合野に入り、側頭葉に移動して、長期記憶として長く定着するからだと言われています。
もし、憶えられないというのであれば、それが短期記憶で終わってしまっていて、長期記憶になっていないからなのです。