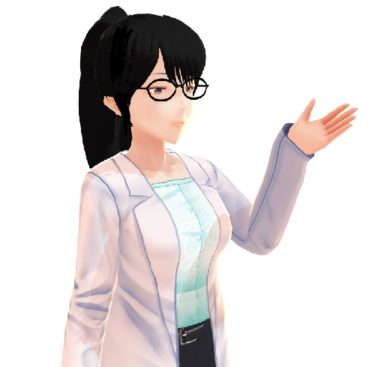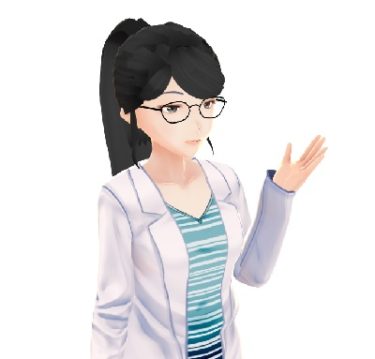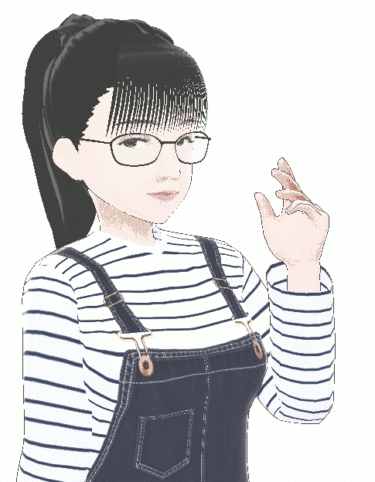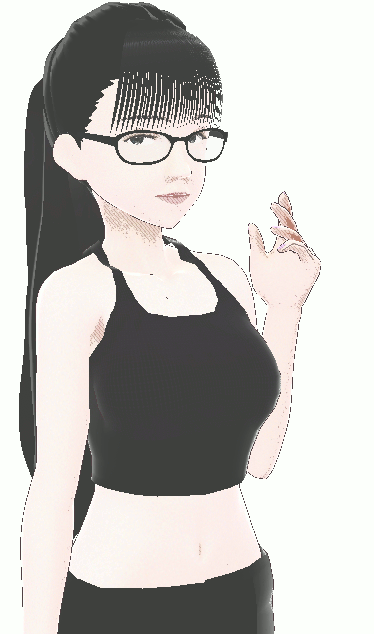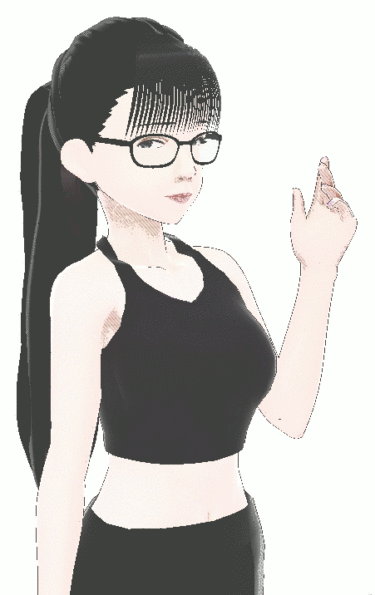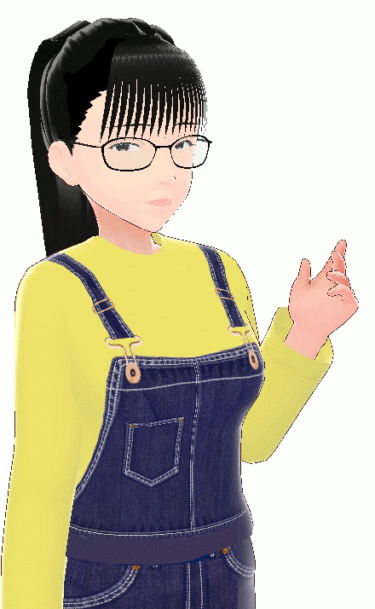『思考のアンバランス』とは、そのまま、考え方や物の見方に偏りがある状態のことになります。
思考のアンバランスとは
考え方や物の見方に偏りがある状態、つまり思考のアンバランスは、意識しないと自分ではなかなか気づけないものですが、わかりにくいので具体例をもって説明しましょう。
例えば、あなたが仕事でミスをしたとします。
仕事でミスをすれば、上司から怒られたり、取引先から文句を言われたり、それじゃなくても落ち込んでなかなかのストレスになりますが、そんな場合を想定してみましょう。
「上司に怒られるし報告は嫌だな」とか、「取引先にどう謝ったらいいのだろうか」と悩んだりすることもあるかもしれません。
それとは別に、いろいろな思考が頭に浮かぶことがあります。
「なんて自分はドジなんだろう」
「あああ、いつも失敗ばかりだ!」
「どうせ次もうまくいかないだろうな・・・」
「こんなに仕事ばかりさせる会社が最低なんだよ」
「適切なアドバイスをしてくれない上司がいけないんだ」
いずれにしろ、自分を責めるか他人を責めるかの違いはあるにしろ、目の前の状況に対して、何らかのジャッジを行っていることになります。
しかもこれらいずれの思考も、客観的な事実に基づいていないのです。
思考のアンバランスは解決にならない
よくよく考えてみてください。
もし、「あああ、いつも失敗ばかりだ!」と思考したとしても、あなたが本当にいつも100%ミスばかりしていたら、会社もクビになっているだろうし、それ以前にまともに社会生活を送れていないはずです。
しかしそうではありません。
実際には、失敗もすれば、成功もしているのです。
「どうせ次もうまくいかないだろうな・・・」という思考にしてもそうです。
何の根拠もない単なる予測でしかありません。
現実的には、ミスをしたという現象のみで、最適な行動としては、ミスの原因を突き止め、再発の防止に努めるしかありません。
明確な根拠や裏付けもなく、物事を決めつけて、そのせいで大きなストレスになってしまっているのです。
気をつけたい思考のアンバランスの例
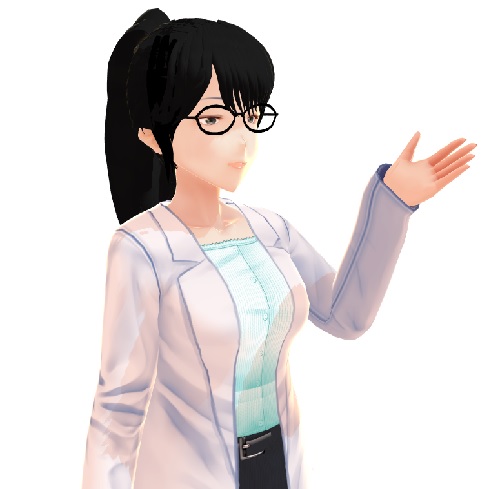
思考のアンバランスがストレスに良くないし、それに気づきにくいというのであれば、なるべくそれに気づきやすくするためにはどうすれば良いのでしょうか。
それには、1つの方法として、思考のアンバランスの例を知っておき、自分が今それに当てはまっていないかをチェックすることです。
思考のアンバランスのパターンは数多くありますが、代表的なものを取り上げてみます。
①「自分のミスでプロジェクトが失敗した」
なんでも自分のせいだと考える思考(個人化)
②「ミスしたのはすべて上司の指導が悪かったせいだ」
なんでも他人や環境のせいだと考える思考(外部化)
③「取引先の部長、私のこと嫌ってるわ」
他人が思っていそうなことを勝手に推測する(読心)
④「私はバカだし、あいつは最低だ」
他人や自分にレッテルを貼る思考(ラベリング)
⑤「ダイエットに失敗したら負け犬だ」
何事も良いか悪いか、白か黒かで決めないと気が済まない(白黒思考)
思い当たる人が多いと思いますが、こうした思考が、ストレスの原因になっているのです。