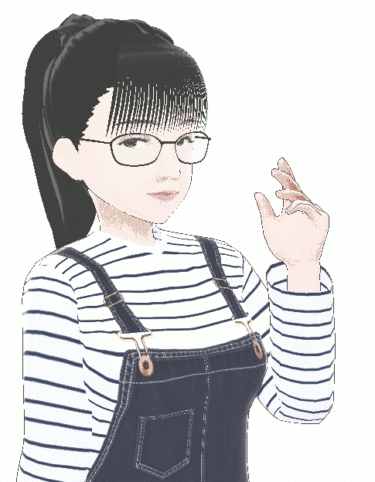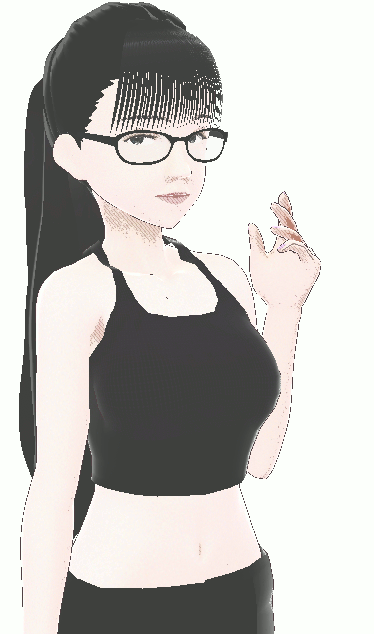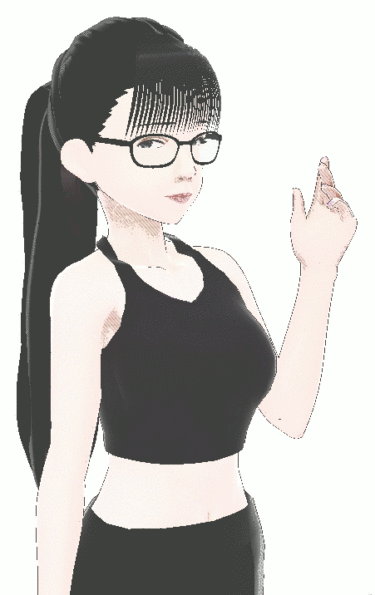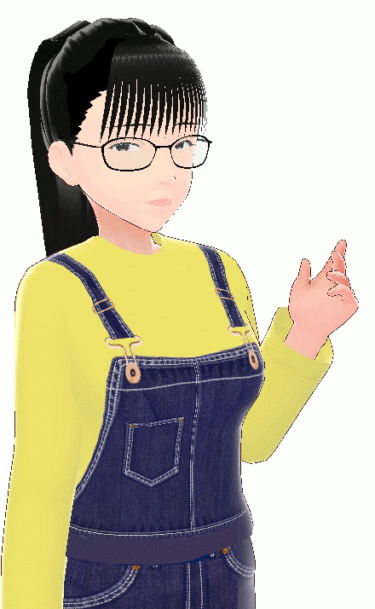プロ野球界で考えてみると、王と長嶋に代表されるように、一流選手にはお互いライバル、好敵手に相当する選手がいたりするものです。
三冠王をとって野村さんにしても、長嶋さんを意識していたようです。
ライバルがいるからこその高み
イチローさんのように、孤高のの天才と言われ、ライバルらしいライバルはいなかったにもかかわらず、多くの記録を塗り替えてきたような天才もいます。
しかし、多くの場合、一流の人にはたいていライバルがいて、ライバルがいるからこそ、切磋琢磨してより高みを目指し、レベルをあげていくものです。
イチロー選手にしても、それ相応のライバルがいたら、もっともっとすごい記録を残していたかもしれません。
アイツには負けたくないという思いから努力を重ね、より技術を上げていくのです。
優秀な同僚がいると引っ張られる
職場で、新しく同僚が入ってきて、その同僚が高いパフォーマンスを見せたら、「よし、自分も負けてられない。自分もがんばろう。」と思う人は多いと思います。
そして、努力しているあなたをみた同僚たちは、自分たちも負けていられない。というようになり、お互いに刺激しあって、全体のパフォーマンスが上がっていきます。
一人で仕事をしていた時にくらべ、同僚が入ってきたことによって、パフォーマンスが上がるということはよくあることなのです。
同僚や仲間などができ、お互いの行動や生産性に影響を与え合い、切磋琢磨しあうという化学反応を、『ピア効果』または『同僚効果』と言ったりします。
例えば、難関校を受験しようとする子供が、学校以外に塾に行くとします。
そこの塾では、もともと難関校を目指している子供たちばかりで、成績優秀で、学習意欲も高い子供たちが集まっています。
すると、子供たちはお互いに刺激をしあって、全体のレベルがアップしていきます。
実際に、スーパーのレジ打ちで従業員に対する調査が行われた結果、同僚の生産性が10%アップすると、他の従業員の生産性が1.5%アップしたという結果もあります。
こうしたピア効果は、優秀な同僚から見られる位置だと発生しますが、見られない位置だと発生しないということもわかっています。
切磋琢磨には、自分と同じか少し優秀ぐらいのライバルが一番いい

優秀な同僚が入ってくることにより、他の従業員の生産性も上がり、全体がレベルアップする場合、正のピア効果と呼ばれたりします。
しかし、逆に競争期間が長かったり、周囲のレベルが高すぎたりすると、嫌気がさしてきて生産性が下がってしまうことがあります。
こうした場合は、負のピア効果と呼ばれます。
例えば、中学生まではクラスでも優秀だった生徒が、レベルの高い高校に進学すると、周りは自分よりもできる生徒ばっかりで、周囲のレベルが高く、自分はダメだという認識を持ってしまい、嫌気がさしてしまい、どんどんと成績が下がっていってしまうというようなケースがあります。
こうした場合は、負のピア効果ということになります。
お互いに切磋琢磨していくライバルというものは、自分とある程度釣りあっている場合に、最大限の効果を発揮するものなのです。