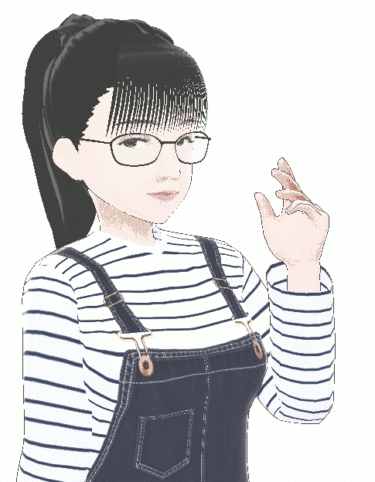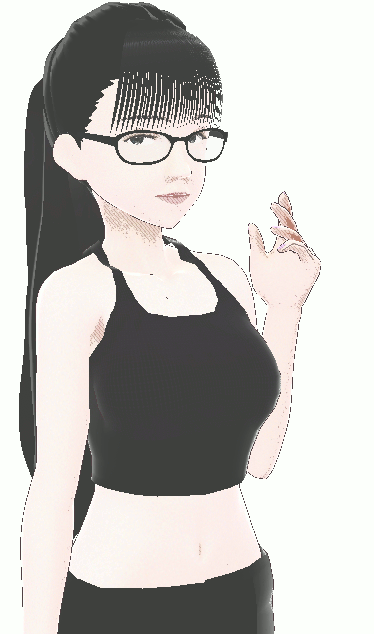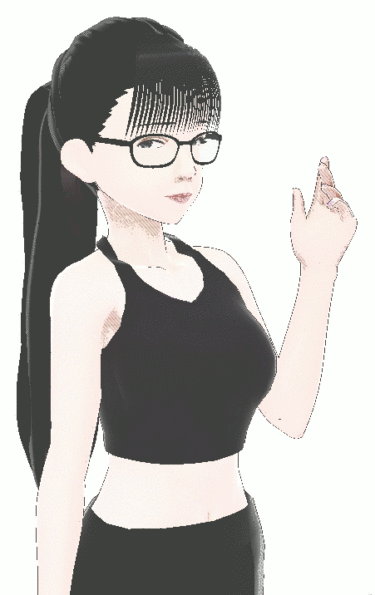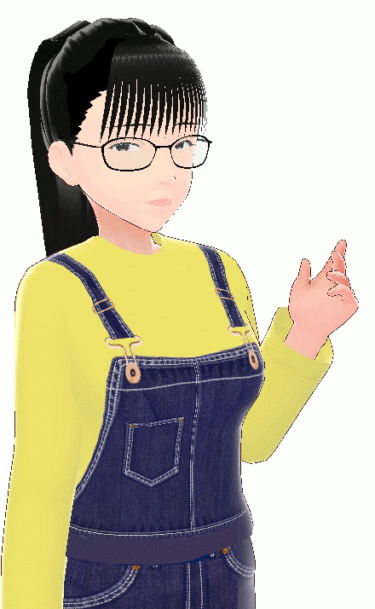日本語には、人の状態を表す言葉にもいろいろと豊富な表現があります。
その中で、比較的よく日常生活においても出てくるものをご紹介していきます。
いわくつき
「あの土地が安いのは、いわくつきの土地だからだよ」
「彼はいわくつきの人だから、気を付けた方がいいよ」
このように、『いわくつき』という言葉は、物に対しても人に対しても使われます。
『いわくつき』と同じような言葉に、『ワケあり』があります。
スーパーなどで「ワケあり商品」として、値引きされて売られているものもありますが、そういった商品をよく見ると、梱包が少し汚れてしまっているためなどのように、値引きされている理由が表示されていたりもします。
『いわくつき』というのは、このように良くない事情があるときに使います。
つまり、何か特別の事情がある、犯罪などの前歴などがあるというような時に使われます。
『いわくつき』を漢字で書くと『曰く付き』になります。
『曰く』は、「先生いわく・・・」といったように、込み入った事情や理由を指します。
「あの人には前科があるらしいわよ」などと言うと、ドギツク聞こえてしまいますが、これを「あの人はいわくつきみたいよ」ということで、ソフトにしかも遠回しに言いたいことを伝えることができるのです。
鳴り物入り
「京大卒の彼は鳴り物入りで入社したけど、期待外れだったよな・・・」
このように、鳴り物入りは皮肉を込めながら言われることが多く、期待外れの場合に多く使われます。
もともと『鳴り物入り』とは、歌舞伎や演劇などで、笛や太鼓などの鳴り物を入れて調子を摂り、にぎやかにすることです。
これが転じて、物事に大げさな宣伝などを伴うことを言うようになりました。
ドラフト1位で、注目を集め、華々しくプロ野球球団に入団したまでは良かったが、なかなかその後芽が出なかったり、すぐに調子が悪くなった選手などに対して、「鳴り物入りで入団したんだけどな・・・」と言われたりします。
つつがない
 「つつがなくお過ごしでしょうか」
「つつがなくお過ごしでしょうか」
というようなお手紙を出したことがある方
「おかげさまでつつがなく暮らしております。」
このようなお手紙をもらった経験がある方もいると思いますが、『つつがなく』は、病気もせず、元気なことを言います。
「つつが」とは、病気などの災厄やわずらいを表します。
これに、「ない」が結びつくので、病がない、異常がない、無事であるという意味になるのです。
『つつがない』は病気がないということですが、それであれば、『つつがある』とすれば、病気で寝込んでいることになるかということになりますが、そうはなりません。
『つつがあります』などという日本語はありません。
素直に、『あいにく体を壊しておりまして・・・』とか『あいにく臥せておりまして・・・』のようになります。