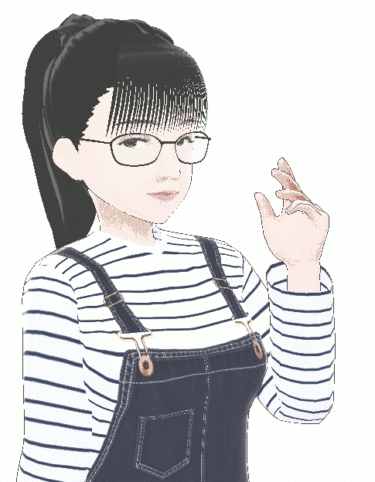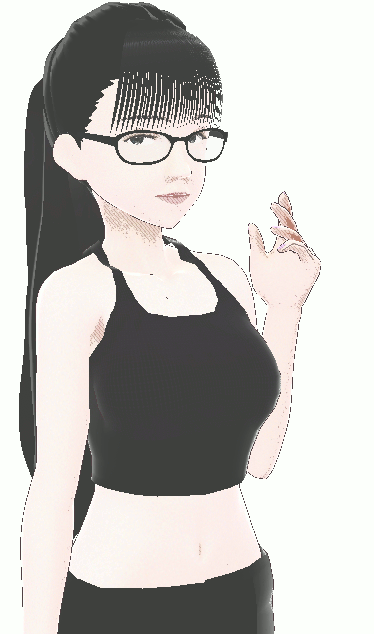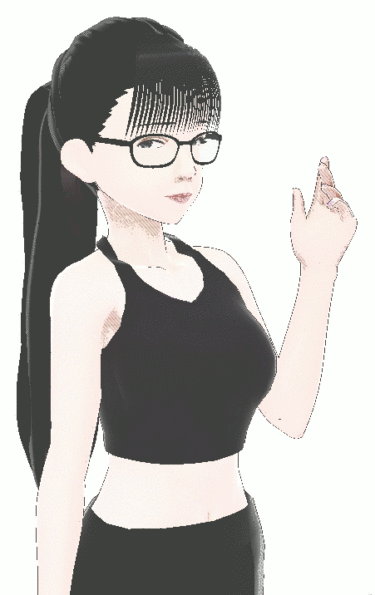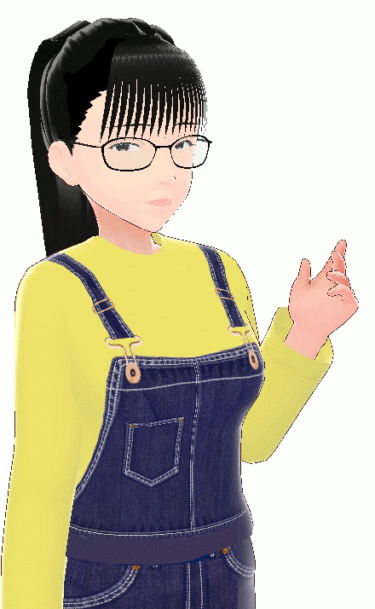なんでも多数決で決めるというのが民主主義の基本です。
もちろん、少数意見に尊重するということが建て前になっていますが、自分が少数意見だったとすると、自分は他の人とは違うのかなとちょっと疎外感をもってしまったりもするものです。
マイノリティを大切にする社会とはいっても、裏を返せばマイノリティはまだまだ疎外感をもっているという裏返しかもしれません。
少し均衡が崩れると劇的な大差になることもある
例えば、選挙なんかで2つの政党があったとして、世論調査をしたところその支持率は拮抗していたとします。
ところが、なんかのきっかけで、若干政党Aのほうが政党Bよりも優位になると、それがあっという間に広がり、1週間間には僅差だったのに、選挙をしてみたら大差となっていたということがあります。
いわゆる風が吹いたなどとも言われますが、ある人の発言によってがらりと流れが変わってしまうこともあります。
沈黙の螺旋
ある影響力がある人が一言発言しただけで、あの人がいうのならば正しいというように、支持が変わってしまう可能性があります。
面白いことに、自分たちが優勢と認識した側はより雄弁になり、劣勢と認識した側は孤立を恐れて沈黙になりがちです。
これは会社の会議などをみてても、あるあるという感じをもつ人もいます。

提案Aと提案Bで支持者が拮抗していたものの、ある影響力がある人が提案Aを支持したとたん、提案Aに乗り換える人がでてきて、支持者が増えるごとに、提案Aを押す声が大きくなっていきます。
寄らば大樹のカゲと言わんばかりに、大勢の人が支持する側についておけば間違いないだろうという、自分をもっていない人たちもこれに加わります。
特に、日本人はそういった傾向が大きいとも言われています。
すると提案Bを支持している人は、よほど自分に自信があるか、強い信念を持っているか、周りを気にしない強い人間でもない限り、多少なりとも自分だけが異端児みたいな気持ちになり、発言しにくくなっていきます。
そして発言することすら止めてしまいます。
その沈黙がより優勢側を勢い図けてしまい、大差になってしまうのです。
それでも意見を言う人が貴重
どんなに少数になっても、果敢に意見を言ってくる人がいます。
そうした人は、どうしても異端児だとか、変人だとかレッテルを貼られやすくなります。
しかし、孤立を恐れずに、自分の信念をもって意見を出してくる人こそ、貴重で変革には欠かせない人材です。
こうした人材をいかに大切にできるかというのも、組織の重要な要素になってくるでしょう。