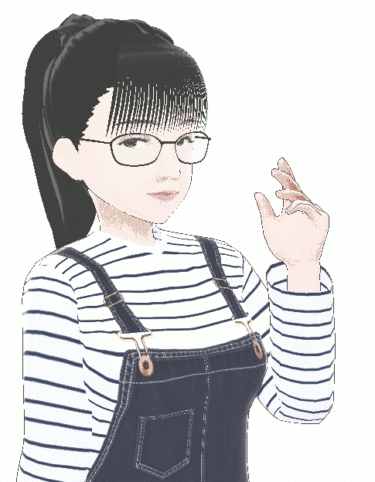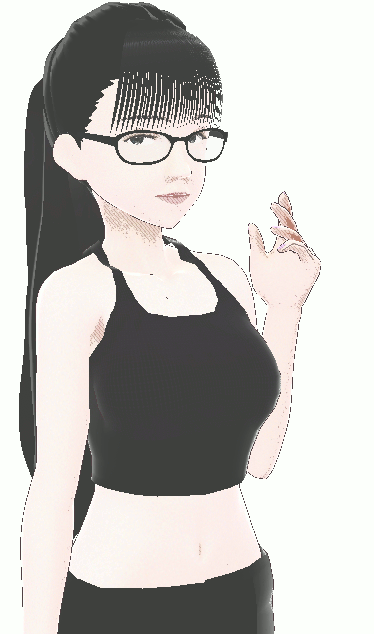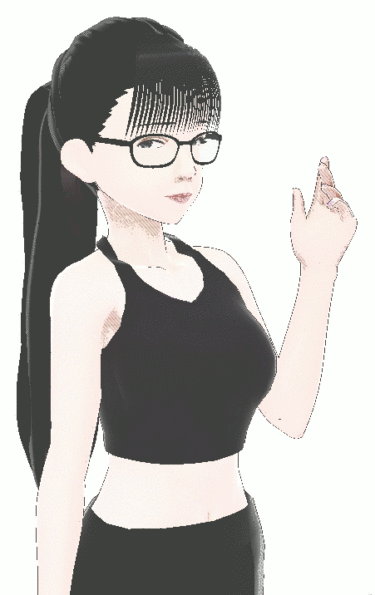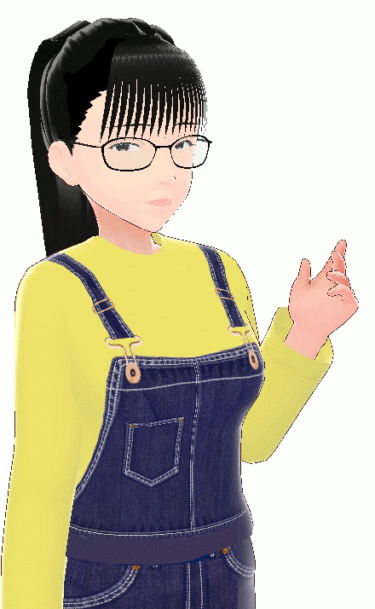発想やアイデアをたくさん持っているアイデアマンは、羨望の的で、誰でもああなりたいと思ったりするものです。
しかし、そんなに急に引き出しが増えるわけでもありません。
引き出しはコピーして盗む
盗むというと、なんか盗作みたいになってしまいますが、実際には自分のアイデアや発想の引き出しを増やすためのコピーをするというだけです、
例えば、博士論文や卒論に、わからないだろうと他の人の論文などをコピー&ペーストして提出すれば、それはパクリであり盗作になってしまいます。
東京五輪にしても、公式エンブレムが盗作なのではないかと問題になりましたが、盗作はいけません。
しかし、自分のアイデアや発想の引き出しを増やすためのコピーであれば、積極的に行ってもよいでしょう。
コピペしたら盗作になるのでは?
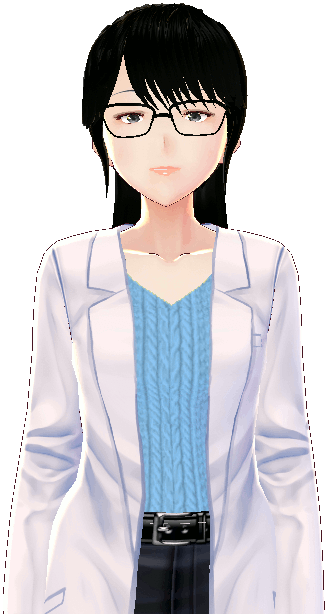
はい、そのままコピペをしたらもちろん盗作になってしまいますし、別に盗作を進めているわけではありません。
コピーすることで、その中から、先人たちが気づいてきた論文の作法や論理構成を学んで引き出しを増やしていくのです。
もちろん、文章は自分の手を使って書き直す必要があります。
人間の脳は何かを模倣することで引き出しが増えていく
そもそも、人間の脳は何かを模倣することによって、新しいことを身に着けるというのが基本プロセスになっています。
だから、新しいアイデアを生む場合でも、まずは真似から入るというのが王道であり、こうしたことを繰り返していくうちに、どんどん自分の中で発想やアイデアの引き出しが増えていくのです。
例えば、会議ですばらしいプレゼンをしたいと思うのであれば、自分が仕事ができる人と思っている人の企画書を借りるなり、パワーポイントの資料を見せてもらうなどして、それを書き写してみると良いでしょう。
いざ書き写してみると、単に見たり、あるいは読んでいるだけでは気づかないような思考法やリズムに気づけたりするものです。
たとえば、AERAや東スポの見出しなどをみても、センスある駄洒落が入っていたり、ハッとするような一目をひく見出しであったりします。
印象に残る言い回しになっていたり、時にはツッコミたくなるような言い回しになっていたり、よくこんな発想ができるなと思いますが、こうしたものを研究していくうちに、AERAや東スポに出てくる見出しを作るような思考回路ができてきます。
そうすると、自分の中に新しい引き出しが増えていきます。
デスクの上で、ウンウンと頭をひねって考えているよりも、いいなと思う見出しを何十個、何百個書き写していると、だんだんその見出しを作った人の気持ちになっていきます。
学ぶことは、真似ぶからきているとも言われていますが、他人のものをコピーするところから思考回路の引き出しを増やしていくのが効率的なのかもしれません。