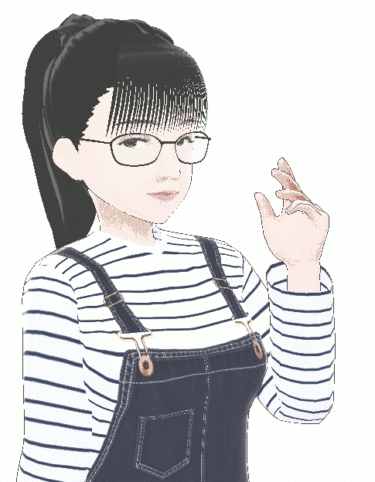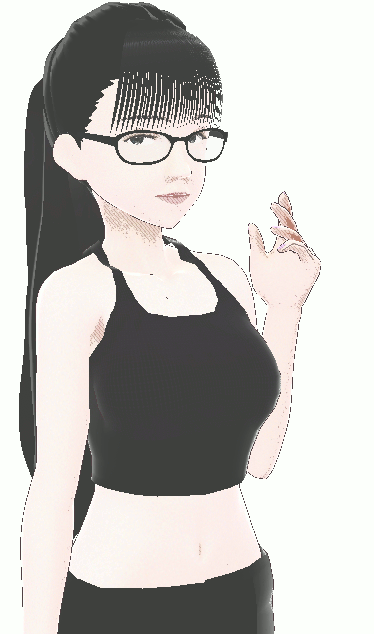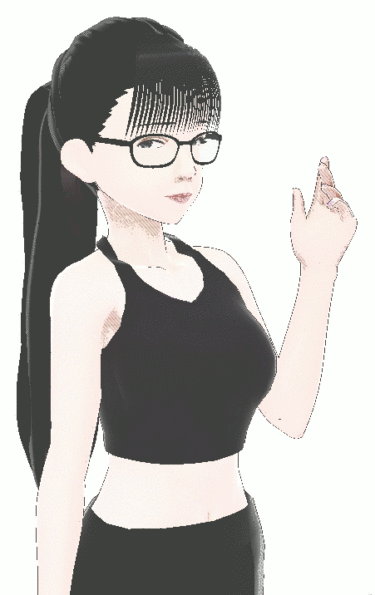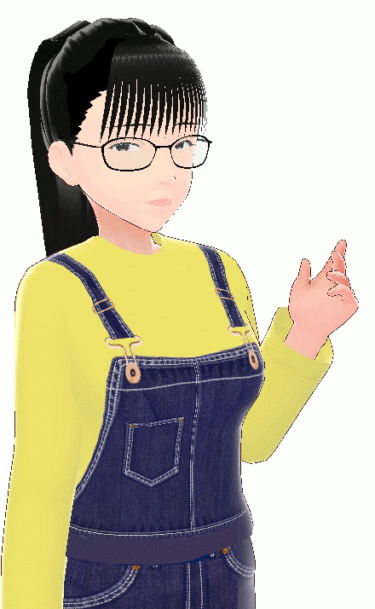半表半裏(はんぴょうはんり)は、漢方ででてくる概念です。
漢方では、病気の原因である細菌やウイルスである外邪が体の中に侵入した際に、病位が体の表裏のどこにあるのか、病勢はどうなのかといった点が判断されます。
半表半裏証
漢方医学・中医学では、人の体を大きく3つの層に分けて考えます。
表、半表半裏、裏の3つですが、これは病位の深浅を区別する指標になります。
体表である皮膚や関節、筋肉、頭部や骨といった部分は「表(ひょう)」になります。
これに対して、呼吸器系や胃・腸といった中空の内臓・臓腑、血脈、骨髄は「裏(り)」になります。
そして、表と裏の中間にある実質臓器が「半表半裏(はんぴょうはんり)」になります。
そして、この半表半裏に病があることを半表半裏証と言います。
風邪の時の半表半裏
例えば、風邪で考えてみると、まず風邪をひくとその初期段階では、症状は表に現れます。
つまり、寒気や発熱、肩こりや関節のこわばりなどがこれに該当します。
そして、病気が進行していくと、裏である臓器に症状が出てきて、咳や痰、食欲不振や嘔吐、下痢、腹痛、便秘などといった症状が起こってきます。
つまり、表から半表半裏へと移っていきます。
そして、さらにこじらせると、腎臓や心臓・肝臓といった実質臓器である半表半裏へと症状が現れてきます。
漢方の病状の考え方

漢方医学では、病状が表にあるか、裏にあるかで、病気の進行度に応じた漢方薬が使い分けられています。
風邪をひいたとき、最初はちょっと寒気がしたり喉が痛かったりして、そのうち熱がでてきて、咳や痰がでてくるという経験をしている人も多いかと思います。
表証のうちは、皮膚の炎症やかゆみ、発熱・寒気、のどの痛みや頭痛、筋肉・関節の痛みなどが現れてきます。
普通の風邪やインフルエンザの初期症状になります。
やがて、表証から半表半裏証や裏証になっていくとともに、腹痛が起こったり、咳や痰がでてきたりします。
表証・半表半裏証・裏証を脈で見分ける
現在の病位が、表証・半表半裏証・裏証のどれなのかを見分ける一つの方法に、脈診があります。
漢方では、脈をみて、その脈が浮なのか沈なのかで判断します。
表証の場合は、脈が浮となりますが、これは、指を軽くあててもわかる脈です。
半表半裏証の場合は、脈が弦となりますが、これは脈が弓の弦のような上下動の少ない突っ張った感じの脈です。
裏証の場合は、脈が沈となりますが、これは、指を強く圧さないとなかなかわからない脈です。