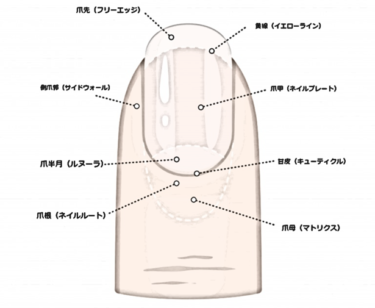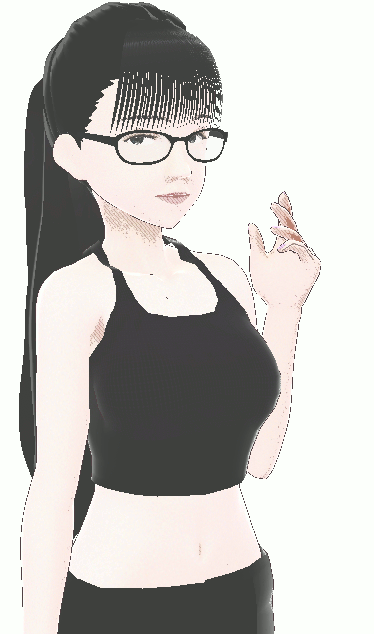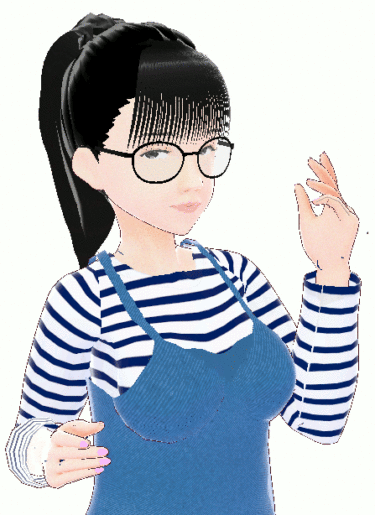太っている人に対して、厳しい人は、自分の体重管理もできないような人はダメ人間だと決めつけてしまう人もいます。
しかし個人個人体質もありますし、そんなことで人を決めつけるべきではないのです。
摂取カロリーを増やしたって太るわけじゃない
太るのは摂取カロリーが増えたからなのでしょうか。
実際に1990年から2010年にかけて米国全国健康・栄養調査(NHANES)が行われていて、そのデータでは、摂取カロリーの増加と体重の増加に相関関係はないと結論づけられています。
イギリスでも、摂取カロリーの増加も、摂取脂質量の増加も、肥満とは関係なかった、つまり因果関係はないと結論づける報告がされています。
人間の体は、どうも「摂取カロリー」ー「消費カロリー」=「体脂肪」というように、熱力学の第1法則(エネルギー保存の法則)のように単純にはいかないのです。
なぜ熱力学の第1法則のように簡単にいかないのか
そもそも、消費カロリーだけに絞っても、難しい話です。
体温維持、熱の発生、蛋白質の合成、骨や筋肉の新たな形成、脳の活動、心拍数や拍出量の変化、消化器官での消化作用、解毒作用、排泄など、消費するカロリーも、思いつくままにあげてもごらんのとおり、次から次へと出てきます。
脳はよくエネルギーを使う器官であり、肉体的な運動をしていなくても、頭脳労働だけでもかなりのエネルギー消費があるのです。
確かにカロリー資源で最初は体重も減るけど

摂取カロリーを制限していくと、確かに1週間で体重は落ちていきます。
1日の摂取カロリーを500kcal減らしたとすると、1週間で0.45kgの脂肪が落ちます。
しかし、これを200週間も続けたら、理論上は体重が0になってしまいますが、実際にそんなことはありません。
人間の体は、総摂取カロリーを制限することで、素早く対応しますが、それは一時的なものでリバウンドしやすいのです。
摂取カロリーを減らし、体重を減らしていうと、食欲を増進させるホルモンであるグレリンの分泌量が大幅に増えてしまいます。
また満腹ホルモンの分泌量も減ってしまいます。
その結果、極端な食事制限によるダイエットを行うと、空腹を感じることが覆うなったり、満腹を感じづらくなり食欲が高まってしまい、せっかくダイエットしても、リバウンドしやすくなってしまうのです。
急激に極端なダイエットをすると、摂取カロリーが急に少なくなったことで体は自分自身を守ろうと、エネルギーの消費節やっくをするために、エネルギー総消費量がすぐに減ってしまい、その状態が続いてしまいます。
そしてもっとエネルギーを摂取しなければいけないと判断した体は、空腹のサインを出すようになります。
無理に原料をすると、制御機能を持っている前頭葉皮質の活動が弱まってしまい、食べ物に対する欲求を抑えるのが難しくなってしまい、ついついリバウンドしてしまうのです。
参考:Am J Med. 2014 Sug; 127(8): 717-27
Ladabaum U et al.
Obesity, abdominal obesity, physical activity, and caloric intake in us adults: 1988 to 2010.