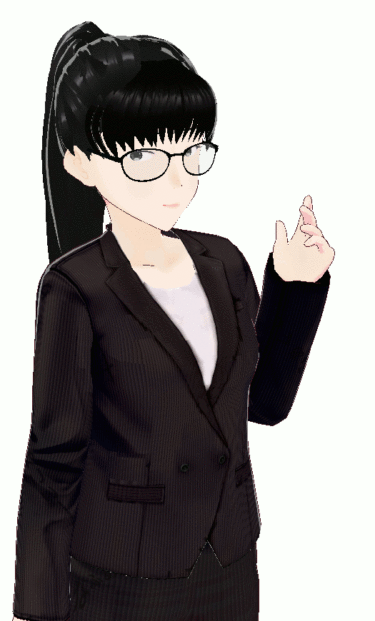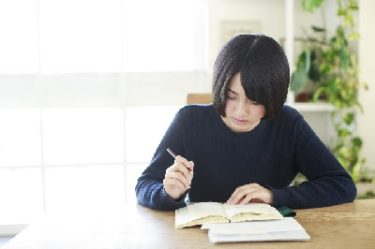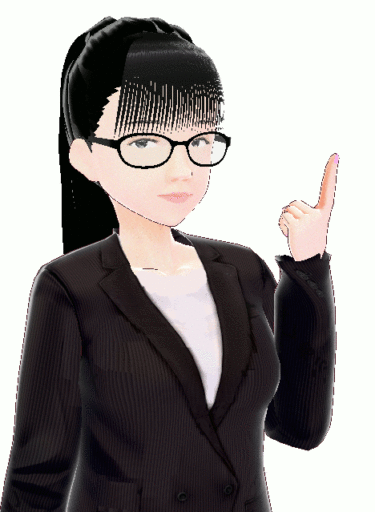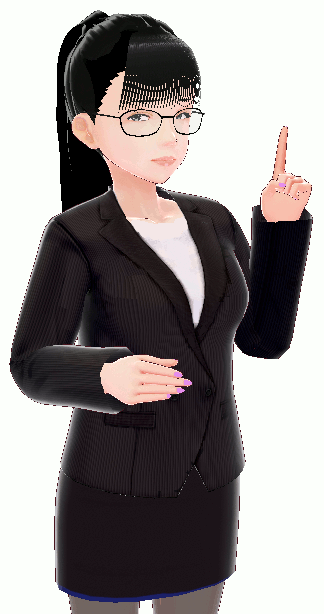アイデアとは、どのようにして産み出されるのでしょうか。
アイデアって何?
アイデアとは何かということで、gooの国語辞典で調べてみると、次のようになっています。
1.思いつき。新奇な工夫。着想。「―が浮かぶ」
2. イデア。観念。理念。
米国の大手広告代理店で多くのメジャー企業広告を担当し、多くの広告賞を受賞しているクリエイティブ・ディレクターであるジャック・フォスター氏は、『アイデアは、既存のアイデアの組み合わせ』と定義しています。
つまり、アイデアは、知識やインプットされた情報を組み合わせて産み出されるものということになります。
アイデアを出す方法
アイデアは、自然に天から降りてくることがあります。
しかし、それを待っていたのでは、いつアイデアがでてくるかわからず、できれば、もっと能動的に意図的にアイデアを産み出したいものです。
アイデアというと、アイデアマンとか天才の専売特許のようなイメージもありますが、アイデアを産み出しやすいプロセスを通していくことで、誰でもアイデアを産み出すことができます。
そのためには、ジャック・フォスター氏は、『アイデアは、既存のアイデアの組み合わせ』と言っているとおり、まずはアイデアを産み出すための知識や情報のインプットが必要になります。
そしてその知識や情報を加工することで、新しいアイデアを産み出そうと試みます。
そうしているうちに、アイデアが頭に浮かんできたりしますので、出てきたアイデアについて、評価し、試行していきます。
ここで、インプットするのは知識だけでなく情報で、単に本や新聞、口コミなどによる知識だけにとどまらないものということになります。
それでは、どんな情報をインプットすればいいのかということですが、思考に新しいパターン形成を促すような情報を意識的に生活の中に取り込むことが大切になってきます。
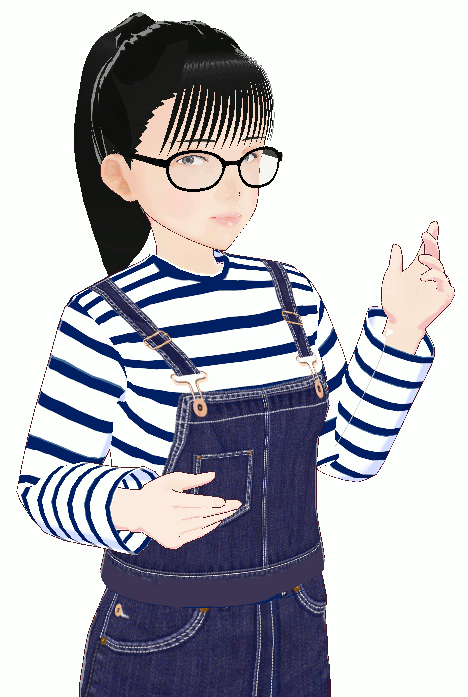
なぜ他分野のことをやるといいのか
よく脳の活性化には、今までにない新しい分野に興味を持ち、挑戦していくことが良いと言われますが、なぜなのでしょうか。
人間の脳は、似たようなインプットをした場合、同一のインプットであると判断したり、既成概念でその情報を処理しようという性質を持っています。
これでは、なかなか新しいアイデアは産まれてきません。
情報に対して、いかにゼロベースな視点で捕らえることができるかがカギになってきます。
ワンパターンの思考で生活をして、それに慣れきっていると、様々な情報をインプットしても、それに対して既成概念を形成しやすくなるので、新しいアイデアは産まれてきにくいのです。
だからこそ、今までにやったことがない趣味に没頭したり、興味がなかったスポーツに興味を持ってみたり、今まで携わったことがない分野の本を読んでみるなどすることで、情報をゼロベースな視点でみることができるようになり、視野も広がり、新しいアイデアが産まれやすくなるのです。