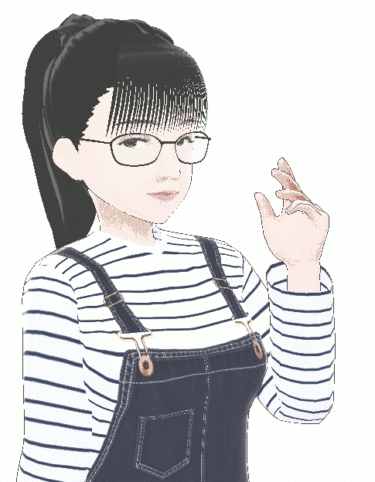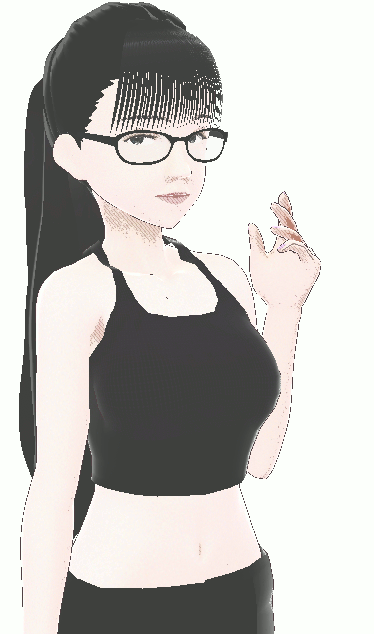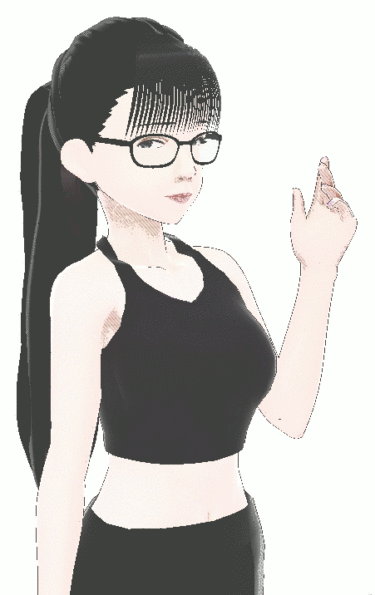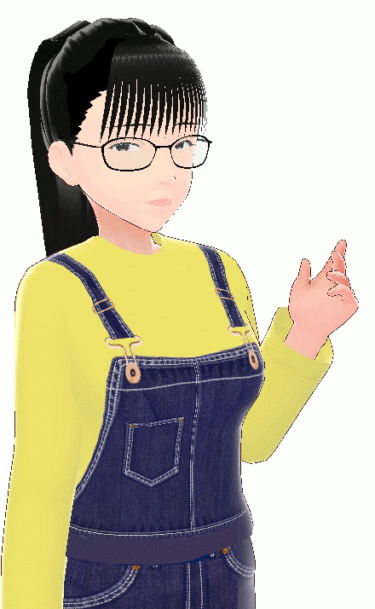糖質の多い食事を続けていると、血液ハドロドロになり、血管は傷つきやすくなります。
毛細血管は赤血球がやっと通れる細さ
特に毛細血管は、血管の内側の内皮細胞と、それを取り囲んでいる周皮細胞でできていますが、毛細血管という名のとおり、非常に細くその直径はわずか100分の1㎜ほどです。
これは血液中を流れる赤血球とほぼ同じ大きさです。
赤血球は折りたたまれるように変形することができるので、かろうじてこの毛細血管を行き来することができるのです。
糖をとりすぎると赤血球が毛細血管を通れない
糖質が多い食事を続けることで、血液中が常に糖分が多すぎる状態になります。
こうなると血糖値を下げるインスリンの働きも弱くなってしまい、糖尿病になってしまいます。
赤血球には酸素を運ぶヘモグロビンがありますが、これにブドウ糖が結合してしまうと、赤血球は弾力性を失い、硬くなってしまいうまく変形できなくなってしまいます。
変形することでかろうじて毛細血管を通り抜けていた赤血球は、毛細血管を通過できず、体の隅々にまで酸素や栄養がいきわたらなくなってしまうのです。
さらに糖の成分によってベタベタと赤血球同士がくっついてしまい毛細血管を通り抜けできなくなります。
すると、酸素や栄養がいきわたらないだけでなく、血管壁が傷ついてしまい、穴があくなどダメージを受けてしまいます。
糖の摂りすぎで毛細血管が痛むと体に不調が

糖の摂りすぎで毛細血管が傷むと、血糖値が上がり、糖尿病になっていきます。
高血糖の状態が長く続くと、特に毛細血管が傷ついていき、毛細血管が多くある神経細胞、目、腎臓といった部分に支障がでてきます。
糖尿病により失明したり、腎臓が悪くなったりするのは、こうした部分に毛細血管がたくさん集まっているからでもあります。
毛細血管が劣化してできるゴースト血管
ゴースト血管とは、血管に穴があき血液が周囲に染み出るようになってしまった状態です。
つまり血液が流れなくなってしまった血管です。
分かりやすく言うと、穴の開いたホースの中に水を流しているような状態です。
正常な毛細血管では、まっすぐにヘアピンのようにカーブしたところを血液が流れているのが見えますが、ゴースト血管の場合は、形や太さがいびつで、ぼんやりとした形に移ります。
こうなると、すみずみの細胞にまで酸素や栄養がいきわたらなくなり、不調や病気を引き起こす原因になってしまうのです。
毛細血管が弱ると、免疫細胞も必要とする場所へ移動できなくなってしまうため、病原体を抑制する力も低下してしまい、風邪を引きやすくなってりします。
また、いろいろなそしきの老廃物もきちんと回収されずに蓄積していったりして、不定愁訴の原因にもなってしまうのです。